電話応対でCS向上事例
-学校法人 大妻学院 大妻女子大学-ビジネスシーンで必要なコミュニケーション能力を高めるため電話応対技能検定を積極活用
記事ID:C20109

大妻女子大学は、創立以来110年以上の歴史を有する、日本でも有数の規模の女子大学です。今回はキャリア教育プログラムの講座として実施されている、同校の電話応対技能検定への取り組みについてうかがいました。
貴校の概要をお聞かせください。
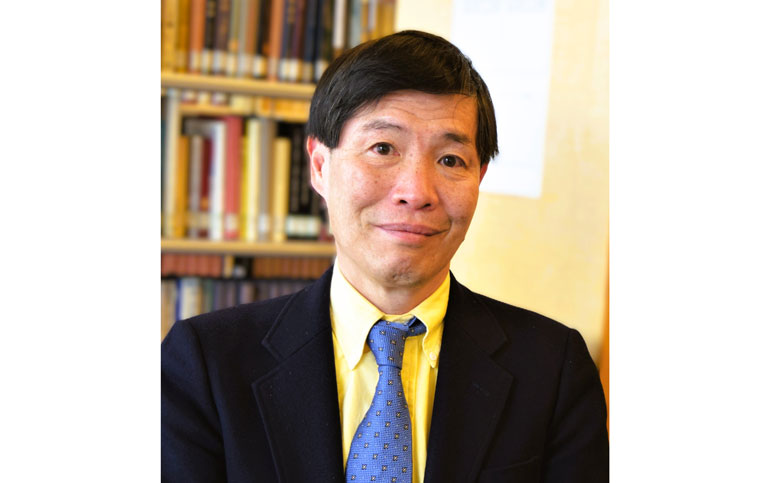
キャリア教育センター 教授
井上 俊也氏
井上氏:本学は東京都千代田区に本部を構える私立女子大学です。1908年、大妻コタカが開設した裁縫・手芸の私塾が起源となり、現在は家政学部、文学部、社会情報学部、人間関係学部、比較文化学部、データサイエンス学部の6学部、短期大学部、大学院、四つの中学・高校を有する女子高等教育機関となりました。創立の理念は時代が変わっても受け継がれ、自ら学び、実践し、社会に貢献し続ける「自立自存の女性」の育成を目指しています。本学には卒業に必要な履修科目のほか、多様な学びの場が設けられています。大妻マネジメントアカデミー(OMA)もその一つで、本学の全学生のほか、卒業生を含む地域社会の成年女性を対象として、マネジメント能力を高めるための正課外のキャリア教育プログラムです。このプログラムは「営業楽部」「資格取得・スキル育成コース」「キャリアエンパワーメントコース」の三つから構成されており、2025年度は86講座を開講、コマ数では年間500~600コマ程度となります。講座は社会のニーズに合わせて、毎年見直されており、時代に合わせたバラエティに富む内容が強みとなっています。
コミュニケーションの可能性を広げる
教育機関でマナーや電話応対について教育する必要性はどのような点にあるのでしょうか?

電話応対技能検定対策講座の様子
井上氏:電話は誰とでも自由にコミュニケーションを取ることができるツールです。しかし、SNSなどの登場により、限られた仲間内のコミュニケーションが多くなっており、その傾向は若い世代の間で顕著です。一方、電話や手紙といった以前からあるコミュニケーション手段に対して若い世代は苦手意識を持つようで、手紙を受けとっても読み終えたらすぐに捨ててしまうという話を聞いたことがあります。また、電話恐怖症という言葉もあるように、相手が誰か分からない状況で会話が始まる電話は敬遠されがちですが、ビジネスシーンでは今でも重要なコミュニケーションの手段です。学生のコミュニケーションの可能性を広げるためにも電話応対教育が必要であると考え、取り組みを始めました。
電話恐怖症の克服に役立つ
電話応対技能検定に取り組んだ経緯、役立った点などを教えてください。
井上氏:今回、6月5日と12日の2日間にわたり、「電話応対技能検定対策講座」を行いました。初日は90分で、ビジネスマナーや敬語、発声法や電話・対面コミュニケーションに関する講義、2日目は40分の講義のあと、4級の検定を行いました。これはOMAのプログラムの一つとして5月に開講した「ビジネスコミュニケーション入門講座」と連動して実施したもので、マナーや敬語を学びたい、資格を取得したい、という学生が受講してくれました。ここにいる佐藤さんも受講生の一人です。
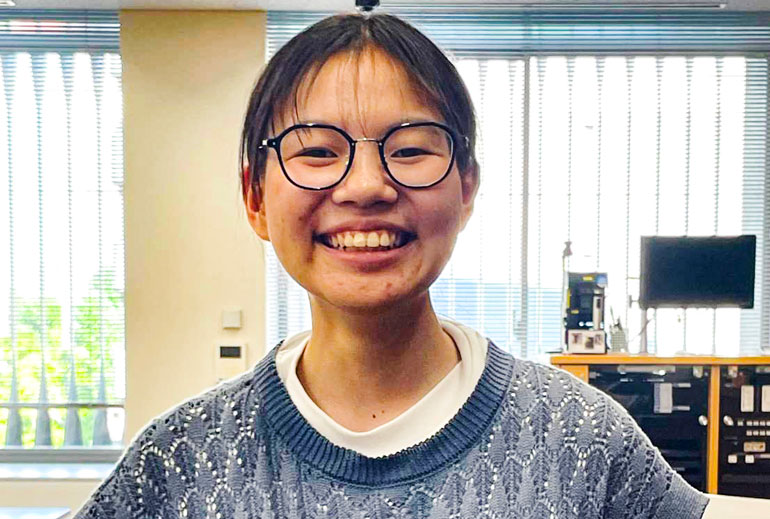
家政学部食物学科
佐藤 鈴蘭さん
佐藤さん:実は私も、これまで電話恐怖症気味になっていました。電話がかかってきても「どこの誰がかけているのか分からない。なんて答えればいいかも分からない。だから出たくない」といった思いがあり、また、「相手に失礼があったらどうしよう」と悩んでいました。こうした講座で敬語やマナーを学び、かけ方や受け方を理解することで電話恐怖症が治り、話せるようになると思い受講しました。当初は、相手を不快にさせない電話応対ができれば十分と思っていましたが、電話応対コンクールで応対する方の映像を見て、自分も人の心を動かすような温かい電話応対ができるようになりたいと考えるようになりました。
“ 就活に有利 ” 以上の学びがある
講師の方にうかがいます。講座を実施した感想と、電話応対教育を行う意義について教えてください。

講師(オフィスポラリス 代表)
白井 裕美氏
白井氏:講義では正しい答えだけでなく「なぜなのか」についても伝えるよう心掛けました。例えば電話応対では「離席中」という言い回しをよく使います。ビジネスの場面で一般的に使う言葉ですが、耳で聞いたときに伝わりにくいため、「席を外しています」といった方が分かりやすいということがあります。これは書き言葉のままで音声化するという日本語の特性の一つであり、その弊害の一例として説明しました。このように具体的なスキルの習得とともに、言葉に対する知識を深めてもらえるよう工夫して講義を進めました。
今回、講座を始める際に受講理由を尋ねたのですが、「アルバイト先でリーダーになったのでしっかりした言葉づかいができるようになりたい」「アルバイト先でお客さまや先輩と会話する機会が多いので敬語を身につけたい」といったように、こうなりたいという姿を思い描いて参加されていることを知り、とても驚きました。電話応対技能検定は丁寧な言葉づかいやビジネスマナーが学べ、就職活動に有利な検定です。ただ、それ以外にも幅広いチャレンジができる学生だからこそ学べることがたくさんあります。話し方や聞き方はもちろん、日本語の特性など言葉の成り立ちを理解した上でコミュニケーション上の試行錯誤を繰り返すことは、ビジネスシーンで必要なコミュニケーション能力を高めることにつながります。若い人たちが電話恐怖症といった不安な状態になるのも、電話での話し方が分からないからではないでしょうか。ですから電話応対ができるかどうかよりも、まずは知識として知っているかどうかが重要だと言えます。そうした意味で、このような機会に話し方や聞き方を学ぶことは非常に意味があると感じています。
“ 電話応対に強い学生 ” の評価をブランドに
最後に、今後の取り組みをお聞かせください

電話のかけ方、受け方を体験してみる
佐藤さん:私は飲食店でアルバイトをしているのですが、今後は電話を取る機会が増えてくるので、そうした際にかけてきたお客さまのことを考えてしっかりとした応対をしたいと思います。特に敬語は、社会人になる上で絶対に欠かせないものですので、これからも継続して学んでいくつもりです。

電話応対技能検定4級を受検
井上氏:電話恐怖症という言葉が広く知られるようになる中、本学の学生は電話応対を率先して学んでいるということが対外的に伝われば、それは一つの価値、ブランドになるかもしれません。そうしたことも視野に入れながら、学生のコミュニケーション能力の幅を広げることを目標として、今後も電話応対技能検定の講座を継続し、12月にはまた4級検定を実施する予定です。
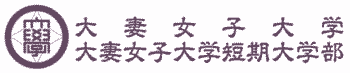
| 法人名 | 学校法人 大妻学院 |
|---|---|
| 創立 | 1908年(明治41年) |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町12番地 |
| 理事長 | 屋敷 和子 |
| 学長 | 市川 博 |
| 学部・短期大学 | 家政学部、文学部、社会情報学部、人間関係学部(2026年 に人間共生学部へと改組予定)、比較文化学部、データサイ エンス学部、短期大学部 |
| 大学院 | 人間文化研究科 |
| URL | https://www.otsuma.ac.jp/ |
関連記事
-
![-学校法人 国際総合学園 国際ビジネス公務員大学校-<br>実社会に貢献するスペシャリスト育成のため電話応対の極意を学ぶ]()
2024.08.26 公開
-学校法人 国際総合学園 国際ビジネス公務員大学校-
実社会に貢献するスペシャリスト育成のため電話応対の極意を学ぶ国際ビジネス公務員大学校は福島県郡山市の私立専門学校です。新潟市に本部を置くNS...
-
![-株式会社アイグランホールディングス-<br>日替わりで社員がオペレーターに従事 コールセンターを会社の最大の武器に育てたい]()
2024.05.28 公開
-株式会社アイグランホールディングス-
日替わりで社員がオペレーターに従事 コールセンターを会社の最大の武器に育てたい株式会社アイグランホールディングスは本社を広島市に構え、全国規模で保育事業やフィ...
-
![-学校法人伊勢学園グループ 伊勢学園高等学校-<br>全学年で品格やマナーを身につける「教養」の授業を実施、もしもし検定受検で即戦力になる人材を育成]()
2023.12.25 公開
-学校法人伊勢学園グループ 伊勢学園高等学校-
全学年で品格やマナーを身につける「教養」の授業を実施、もしもし検定受検で即戦力になる人材を育成校訓「美しく生きる」「強く生きる」を基に、学力、品格、個性の三つの柱を掲げて、多...
-
![-株式会社しちだ・教育研究所-<br>相手の気持ちをおもんぱかり、「最高の教育には、最高の応対を」を実現したい]()
2023.08.25 公開
-株式会社しちだ・教育研究所-
相手の気持ちをおもんぱかり、「最高の教育には、最高の応対を」を実現したい国内だけでなく、海外でも子どもの才能を伸ばす「七田式教育」の教室を展開している株...
-
![-株式会社長野自動車センター-<br>「おもてなし指導員」と「お客さま満足度アンケート」で、 選ばれる自動車教習所を目指す]()
2023.05.25 公開
-株式会社長野自動車センター-
「おもてなし指導員」と「お客さま満足度アンケート」で、 選ばれる自動車教習所を目指す1960年に長野市内で設立し、2020年に60周年を迎えた株式会社長野自動車セン...






































