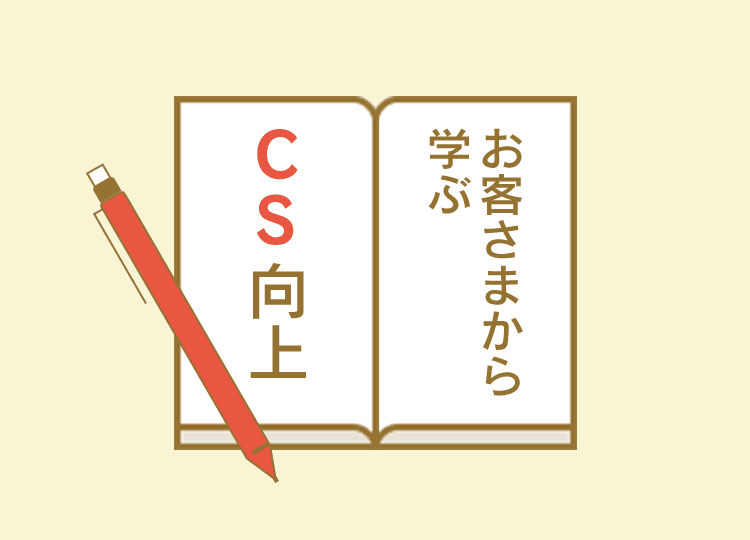電話応対でCS向上コラム
第95回 「説明が届かない」記事ID:C10038
ビジネスパーソンに求められる必須の能力の一つが説明力です。電話のオペレーターにとっても、お客さまの信頼を得るには、明快で温かい説明力は必須です。しかし、最近その説明力が劣化しているように思えるのです。IT化が進む中で、人間が説明する場面が減ったためか、それともコロナ禍の自粛の影響なのか。気になる説明力の現状について考えます。
言葉での説明が下手になった
本誌連載の第54回で、「最近は電話での道案内が下手になった」と書きました。すると、「スマホの時代に電話で道を訊いてくる人なんかいませんよ」とのお叱りがありました。しかし、現実には、説明力が確実に落ちているのです。そのことはすべてに影響しているのです。
つい先日、都内のデパートでのことです。売り場の女性にトイレの場所を訊きました。彼女はカウンターの中から、方向を指さして「あそこの白い壁の奥にあります」と教えてくれました。しかし、教えてくれた先にあったのは女子トイレだけで、男子トイレはその階にはなかったのです。やむなくまた別の人に訊いて、階段を上り、そこでまた訊いて、目的のトイレに辿り着くまでに十数分かかりました。
もう1件は東京の都心の街頭でのことです。ある会合に出るのに、場所が分からずスマホで探したのですが見つかりません。時間に遅れそうなので、ちょうど目についた交番に駆け込みました。目的の建物の所番地を言って訊きますと、若いお巡りさんがすぐにポケットから自分のスマホを取り出し、手際よく地図画面を出して私に示してくれました。ところが、それは私が迷ったのと同じ画面だったのです。昔の交番のお巡りさんは、地域の情報を熟知していました。道を訊くと、立ち所に大きな住宅地図をとり出して懇切に教えてくれたものです。この時もそうして教えてくれるだろうという期待がありました。しかし違いました。すべてスマホなのです。言葉での説明はほとんどありませんでした。
こうした傾向が、最近増えているように思います。案内は説明力の基本です。説明とは、相手が何を知りたいのか、何が分からないのか、置かれた状況まで察してそれに応えられなければなりません。
コミュニケーションとは説明力
考えてみますと、人間社会は説明という行為で成り立っているように思います。教育も科学も、ビジネスも医療も、スポーツも娯楽も、すべては「説明」なくしては成り立ちません。知識も技能も考え方も、しっかりとした説明があって初めて、普及し継承されるのです。
電化製品など、多少なりともメカニックな商品には、トリセツと言われる取扱説明書がしっかりついていました。ところが、最近のペーパーレスの波に乗って、そのトリセツも淘汰されつつあります。これからは、ますます口頭での説明力が問われることになるでしょう。
とかく批判もされる一国の首相の施政方針演説は、国をどう動かして行くかの最も大事な説明です。しばしば問題となる、政治家たちの公約や、法の裁き、外交や経済の交渉ごと、また企業トップの訓示なども、一つ一つが重い言葉で語られるべき説明です。そして、皆さんが日々お客さまと交わす会話のほとんども、大事な説明なのです。
説明は努力で上手くなれる
説明は分かりやすくなければいけません。その巧拙は天性の資質より努力で磨かれるのです。説明は、大別すると①知識を説明する。②考え方を説明する。③技術的なことを説明する。の三つに分けられます。自動応答システムやAIの説明には、まだまだ不満が残ります。人間の応対者に期待する「説明」には、事前に確認し把握しておかなければならないポイントがあります。
1. 相手が知りたいことは何か
2. なぜそれを知りたいのかの理由
3. そのことについてどこまで相手が知っているかの確認
4. 今相手が置かれている状況
以上の四つです。
説明には優しさ親切さが大事
マニュアルやインターネットに慣れますと、そこには便利な反面、大きな
お客さまが満足してくださる説明には2.3.の確認が必要です。そしてお客さまの最後の満足は、「優しく親切な説明であった」にあると思います。
※

岡部 達昭氏
日本電信電話ユーザ協会電話応対技能検定委員会委員。
NHKアナウンサー、(財)NHK放送研修センター理事、日本語センター長を経て現在は企業、自治体の研修講演などを担当する。「心をつかむコミュニケーション」を基本に、言葉と非言語表現力の研究を行っている。