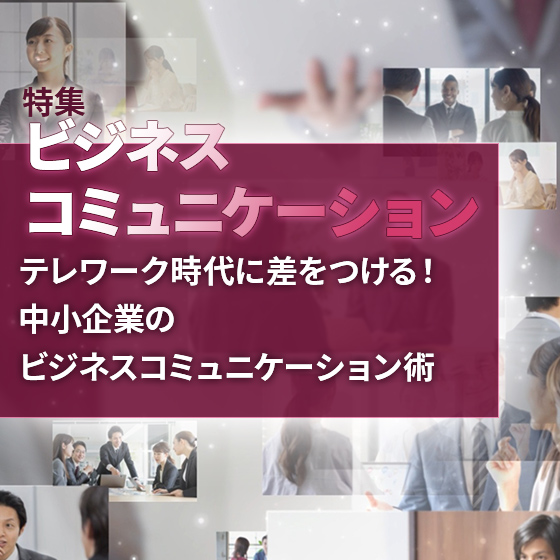電話応対でCS向上コラム
勤怠管理とは記事ID:C10133
適切な勤怠管理は企業運営の基盤であり、労働時間の適正な把握は法的義務でもあります。本稿では、勤怠管理の重要性や起こりうるトラブル、最新の勤怠管理システムについて解説します。
勤怠管理とは何か
勤怠管理とは、従業員の労働時間を適正に記録し、給与計算や労働基準法に基づいた管理を行うことを指します。労働時間、休憩時間、残業時間、休日出勤の記録を正確に管理することは、企業の法令遵守のみならず、労働環境の健全化にも寄与します。
企業は、適切な勤怠管理を行う義務があります。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)では、どのようなものが労働時間か、どのような形で把握すべきかが示されています。
勤怠管理の重要性
適切な勤怠管理が行われていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
(1) 労働時間の未把握による法的リスク
労働基準法では、企業には労働時間を適正に管理する義務があります。未払い残業や過重労働が問題となり、労働基準監督署の指導や訴訟リスクが発生する可能性があります。
(2) 従業員の健康リスク
過重労働が常態化すると、従業員の健康を損ない、結果として生産性の低下や離職率の上昇につながります。特に長時間労働が原因となる過労死問題は、企業の社会的責任にも関わります。
(3) 給与計算のトラブル
適切に勤怠が管理されていないと、給与計算時に誤りが発生しやすくなります。従業員の不満につながり、労働環境の悪化を招く可能性があります。
勤怠管理の方法と集計作業
毎月の労働時間の把握と給与計算のため、実際に働いた時間を打刻するなどで把握し、労働時間を集計する作業があります。以前はタイムカードの打刻情報をもとに人力で集計していましたが、最近では勤怠システムで打刻を行うと、設定どおりの集計が自動で行われるものもあります。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、使用者が始業・終業時刻を確認。記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。この(イ)の「客観的な記録」として、クラウド型の勤怠システムや、パソコンのログインの時間、入退室記録などを基に勤怠を把握することがあります。
また、やむを得ず自己申告制とする場合は、労働者や管理者に正しく記録することについて十分に説明すること、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすることなど、自己申告制によって短く申告することがないように制限を設けています。
よくある質問 「これって労働時間?」
労働時間の把握が必要だと言っても、例えば移動時間や研修の時間などはどうでしょうか。判断に迷うことも多いと思います。
例えば、このような時間はいかがでしょうか。「制服に着替える時間」「自主的な研修時間」「早めに出てきて準備をしている時間」「時間外に自宅でメールチェックした時間」「出張時の移動時間」などは、判断に迷うのではないでしょうか。これらは、その実態によって労働時間となります。「労働時間は使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間」です。
ガイドラインでは、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとしています。「黙示の指示」とは、いわゆるサービス残業など、明確に指示されていないがやらざるを得なかったり、会社が働いていることを把握しているにも関わらず、業務を終了させなかった時間です。
このような勤怠管理は、企業の健全な運営を支える重要な業務の一つです。適切な勤怠管理を行うことで、法的リスクの低減、従業員の健康維持、労働環境の改善が可能になります。最新の勤怠管理システムを活用しながら、企業の実情に合った管理体制を整えていくことが求められます。

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。