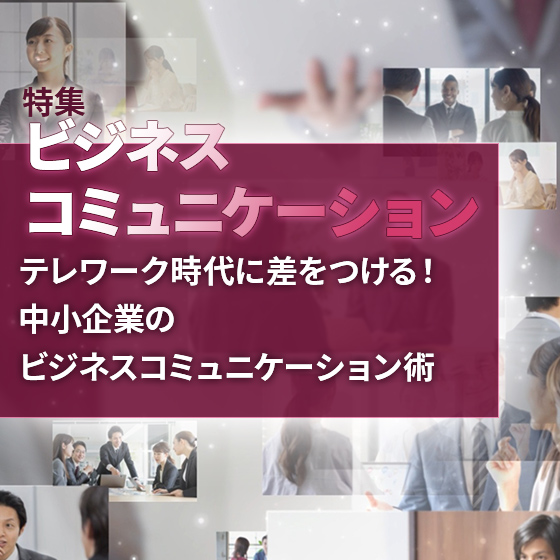電話応対でCS向上コラム
就業規則について記事ID:C10142
「これってどうなってるの?」と感じる休暇や残業、育児との両立支援。実は多くが「就業規則」に定められています。見たことがない方も多いかもしれませんが、働く上で欠かせない基本ルールです。今回は、就業規則の基本と、押さえておきたいポイントについてお話しします。
就業規則とは何か
就業規則とは、会社の中で働く上でのルールを定めた文書のことです。労働時間、休日、給与、退職、懲戒など、働く人にとって重要な取り決めが記載されています。法律上の位置づけとしては、労働基準法第89条に基づく制度であり、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則の作成と、所轄の労働基準監督署への届出が義務づけられています。
特に注意が必要なのは、「書かなければならない項目」が法律で定められている点です。例えば、始業・終業の時刻や休憩時間、休日・休暇、賃金の決定方法、退職の手続きに関することなどが、必ず記載されなければなりません。また、会社の決まりとする場合には記載しなければならないこともあります。
就業規則があることによるメリットは、従業員と会社の双方にあります。従業員にとっては、自分の働く条件が明確になることで、不安や疑問が軽減されます。また、会社にとっては、トラブルの予防や、公平な人事運用の土台として機能します。明文化されたルールがあることで、対応の一貫性が保たれやすくなるのです。
就業規則が無効になるケース
基本的には、就業規則に定めたことが会社のルールとなります。しかし、就業規則があれば何でもできるわけではありません。就業規則で定めた内容が法律に反していたり、公序良俗に反していたりする場合、その部分は無効とされます。法律で定められた基準を下回る取り決めをしても、それは認められないのです。例えば、「残業代は支払わない」「年次有給休暇は理由が正当なものでなければ取得できない」などが記載してあったとしても、それは法律に反していますから無効となります。
また、就業規則に記載がない項目については、基本的には運用することができません。特に懲戒処分や解雇といった重大な処分については、それが正当なものに見えても、「就業規則に明記されていない」という理由で無効とされることもあります。
会社のルールを変更する時は、就業規則を変更することになりますが、「不利益変更」に注意しなければなりません。例えば、今まであった手当を廃止するなど、従業員にとって不利な変更を行う際は、合理性が求められます。従業員の同意を得ずに一方的に変更してしまうと、後々認められずにトラブルにつながることもあります。
育児・介護休業などに関する規程
近年、育児や介護に関する制度が大きく変化しており、それに伴い就業規則への反映も求められています。育児や介護については、育児介護休業規程など、別の規程にする会社も多いですね。こういった規程も併せて労働基準監督署に届出をし、就業規則の一つとして扱われます。
育児・介護休業法は頻繁に改正されるため、就業規則の定期的な見直しも重要です。法改正に対応しないまま古いルールが残っていると、制度の活用を妨げる要因となることもあります。中には、法定以上に充実した独自制度を設けている企業もあり、従業員満足度の向上に寄与しています。
出産や、育児、介護については、部下の方からもよく相談されるポイントではないでしょうか。規程を確認して理解しておくようにしましょう。
多様な働き方に対応した就業規則
時短勤務、テレワーク、フレックスタイム制など、柔軟な働き方が広がる中で、それぞれの働き方に応じたルール整備が必要です。
例えば、短時間勤務は育児や介護に対応する制度として法定化されており、対象者や勤務時間の範囲を明記する必要があります。テレワークでは労働時間や業務の指示方法、費用負担、情報管理のルールなどが求められます。フレックスタイム制も、コアタイムや清算期間の取り決めが不可欠です。就業規則に明記するだけでなく、個別の勤務規程を設けて、制度を適正に運用することが重要です。
多様な働き方への対応は、従業員の満足度向上だけでなく、優秀な人材の確保や定着にも大きく影響します。柔軟性のある制度は、それだけで魅力的な職場づくりの一歩となります。しかし同時に、制度の乱用や不公平感を防ぐためには、明確なルールと、その運用の透明性が不可欠です。制度を「導入すること」だけでなく、「どう運用するか」までを見据えて、就業規則の整備を進めることが、これからの人事労務に求められる姿勢だと言えるでしょう。

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。