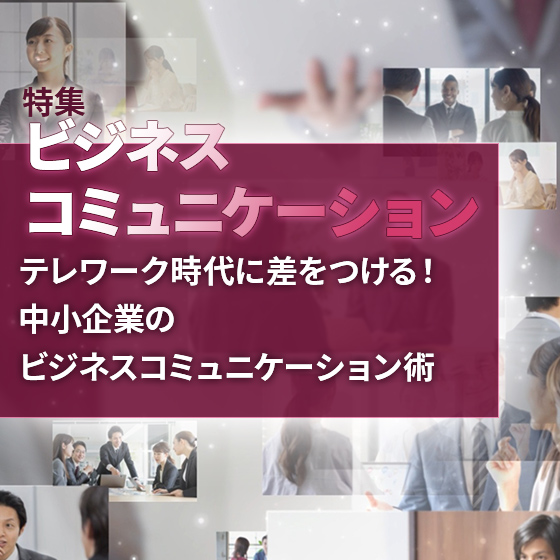電話応対でCS向上コラム
第129回 「『間』こそ命」記事ID:C10132
言葉が伝わり難くなっています。伝達のためのツールは、驚くほど進歩し続けていますが、そこで使われる言葉や話し方は、むしろ退歩しているように思えるのです。言葉の役目は、伝えたいことが、伝えたい人に、平易に確実に伝わらなければなりません。それがそうはならないのです。今どきの話し言葉は、良く言えば自由闊達に、悪く言えば野放図に気ままに使われています。結果として伝わり難いのです。何がそうさせているのでしょうか。
分かりやすい話し方の8つの条件
「伝わってこそ言葉」と言います。そのためにはいくつかの条件があります。1. 相手が知りたいことを話す。2. しっかりした組み立てで話す。3. 聞き手が分かる言葉で話す。4. 聞きやすい発音、発声で話す。5. 聞きやすいテンポで話す。6. 声の表情を大切に話す。7. ポイントを繰り返し話す。そして最も大事なことは8番目で、しっかり「間」をとって話すことです。ところが、この「間」の指導が一番立ち遅れているのです。
『「間」が足りない!』『もっと「間」をとって!』という指導は、読む、話す、を学ぶ時には、必ず言われるはずです。しかし、なぜ「間」が大事かという論理的な指導と、どうすれば適切な「間」がとれるかという具体的指導が、どちらも曖昧なままなのです。
言葉は「間」で理解する
私たちは、聞いた言葉は「間」で理解するのだそうです。耳から入った言葉をすぐ解釈し理解はしません。聞いた言葉は一旦脳の中に溜めておきます。そして0.45秒以上の「間」があった時に、溜めていた言葉を解釈するというのです。
ということは、話し手が0.45秒以上の「間」をとらずに、早口でペラペラ話してしまいますと、聞き手は聞いた言葉を溜めるばかりで解釈できません。つまり、会話やスピーチ、説明の中で、「間」をとることがいかに大事かということです。この説は、もう20年ぐらい前になりましょうか、当時、神戸外国語大学にいらした河野 守夫さんの研究から学んだことです。河野先生は、当時、学生たちの協力を得て実験を繰り返し、0.45秒という解釈の「間」を見つけ出したのです。
すべてに通用する0.45秒の「間」
「間」の存在は、話し言葉に限らず、万物の営みに深く関わってきます。また人間の作り出すさまざまな身体表現、能、狂言、舞踊、演劇も音楽も、茶道も絵画、彫刻、生け花も、建築も写真も、微妙な「間」の表現に命を懸けています。スポーツもまた当然「間」の世界です。
かつて平成の三四郎と呼ばれた柔道家、古賀 稔彦さんをご記憶でしょうか。世界選手権に三連覇、バルセロナ五輪の71キロ級では怪我を押して出場し、見事に金メダルに輝いたその活躍ぶりは、今も鮮やかに脳裏に残っています。古賀さんは、次のアトランタ五輪では惜しくも銀メダルでした。私どもはさらなる活躍を期待していたのですが、その4年後のシドニー大会を前に引退されました。その引退会見はショックでした。「私は最盛期には、相手の襟をつかんでから投げるのに0.4秒でした。それが今は体力が衰えて0.5秒かかるようになりました。だから私は引退を決意しました」。話を聴いた時には、本当に驚きました。古賀さんが言われた0.4秒と0.5秒の間には、河野さんのおっしゃる解釈の「間」、0.45秒があったのです。
令和の今の時代は、情報量が格段に増えています。有限の持ち時間の中に少しでも多くの情報を入れようとすれば、当然早口になります。しかもタイパ※を歓迎する時流の中で、「間」はどんどん削られています。「間」が果たす大事な役割も無視されてしまうのです。
「間」は伝わる言葉の命
伝わる話し方の最大のポイントは「間」です。常に言葉を聴き手の心に届ける気持ちで、ゆったりと話してください。原稿を書き、それを覚えて話しますと、「間」をとったつもりでも、すべて「等間隔の間」になってしまいます。それでは言葉は伝わりません。電話応対コンクールなどで時間を気にしますと、これもまた「間」が犠牲になります。朗読などでは、「間」は言葉を生かすだけではなく、その微妙な「間」によって、「間」そのものが語ることもあります。「間」に表情が出るのです。「間」の重要性、「間」の力を、改めて考えてみてください。
- ※ タイパ
- タイムパフォーマンス(時間対効果)のこと。費やした時間とそれによって得られた効果や満足度の対比。

岡部 達昭氏
日本電信電話ユーザ協会電話応対技能検定委員会検定委員。
NHK アナウンサー、(財)NHK 放送研修センター理事、日本語センター長を経て現在は企業、自治体の研修講演などを担当する。「心をつかむコミュニケーション」を基本に、言葉と非言語表現力の研究を行っている。