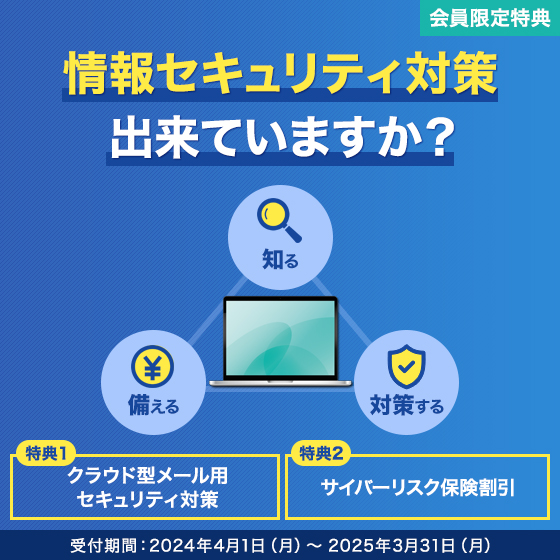企業ICT導入事例
-松本興産株式会社-自社開発のアプリで業務効率を大幅に向上 従業員の“デジタル人材化”を後押しする環境づくり
記事ID:D20039

松本興産株式会社は、自動車や精密機器などに使われる金属部品の切削加工メーカーです。最新設備を擁した製造技術もさることながら、2020年から取り組んできたDXの成果が大きな注目を集めています。デジタル人材をリスキリング※1で育成し、ICTを活用した業務改善で大きな成果を上げた同社で、工場管理部と兼任しながらDX推進の最前線に立つ島﨑凛氏に、同社の取り組みや成果についてうかがいました。
赤字経営からの脱却に向けDXによる業務改善に乗り出す

工場管理部 島﨑 凛氏
金属の精密切削加工・販売を主軸事業とする松本興産は、コロナ禍で業績が悪化し、業務改善を迫られていました。そのためDXに活路を求めた同社ですが、現在、DX推進を担う若手として活躍する島﨑氏は「まさに、その変革期に入社した」と当時を振り返ります。
「私が入社したのは、2020年のことです。コロナ禍の拡大によって当社も打撃を受けて赤字経営となり、コスト削減などの対策を打っていく必要がありましたが、複雑に絡み合った問題も多く、なかなか手をつけるのが難しい状況でした」(島﨑氏)
コスト削減に取り組もうにも、目の前には紙ベースの非効率な業務や予算の制限、そしてベテラン従業員を中心とした変化を好まない企業風土など、改革を阻む壁が数多くありました。とはいえ、メモを転記する際の転記ミスのリスクや、余分にかかる作業時間といったムダも多く、経費や人件費の点からも無視はできないポイントです。そこで経営の改善に乗り出した取締役の松本 めぐみ氏は、まずは少ない予算でも始められるDXに目をつけ、「IoT部門」の名を冠したプロジェクトチームを組成します。
「プロジェクトには松本をはじめとした経営層や部門長クラス、それから適性検査によってIT適性があると判断された従業員が参加しました。私は当時、製品の検査やその記録・管理を担当していましたが、この適性検査でIT適性ありとなり、プロジェクトに加わることになりました」(島﨑氏)
従業員のリスキリングで自社内でのアプリ開発を実現

画像①/島﨑さんが開発した「検査記録アプリ」の操作画面。手書き記入やパソコンへの転記の必要をなくし、工数を削減
松本興産では、過去にも生産ラインをデジタル管理するためのシステムを導入したことがあります。ところが、システムに備わっている機能が多すぎるために、生産現場にいる従業員にとってはかえってわかりにくく、使いにくいシステムだったため、導入は失敗に終わるという苦い経験となりました。この時の教訓から、新設した「IoT部門」のメンバーは、意思決定を行う経営層に加え、現場をよく知る各部門長を中心に選抜されました。その第一歩として取り組んだのが、メンバーのリスキリングです。
「当社では松本が先行してリスキリングを始めた中で知り合った講師の方に依頼し、IoT部門のメンバー向けにオンライン講習をしていただきました。オンライン講習は週に1回開催し、講師の方に弊社の仕事の流れや仕組みを説明した上で、どのようなアプリを作りたいかを相談することから始めました。その後、アプリが完成するまでを指導してもらったのですが、単に作りたいアプリを作るのではなく、制作しながら個々のスキルを上げていき、徐々に自立してアプリ制作ができるように指導していただきました。講座1回あたりの時間は1時間半~2時間でしたが、その時間内に学びきれなかった部分はチャットツールで個別に質問ができたことも習得度の向上に役立ちました。アプリを自社開発するメリットは、外部ツールを導入するコストがかからないことと、自分たちが求める機能をシンプルに実現できる点にあります」(島﨑氏)
その後、アプリはローコード・ノーコード※2で続々と開発され、現在では70ものアプリが内製化されて業務改善に寄与しています。島﨑氏も、外部ITコンサルタントのサポートを受けながらアプリを開発、導入までを成し遂げた一人です。
「私が開発した『検査記録アプリ』は、検査日時や検査内容、不良品の数などを製品検査の担当者がスマホやタブレット端末で入力・管理できるようにしたものです(画像①参照)。それまでは各担当者が紙にメモして後からExcelに転記するという非効率な工程でしたが、検査記録アプリを導入して紙のメモを廃止したことで、作業時間は年間1万時間削減され、1,500万円のコスト削減効果が得られました。導入にあたっては、現場の声を聞きながら項目を追加したり、文字を打つのではなく選択式にしたりと、使いやすさを考慮して工夫を重ねていきました」( 島﨑氏)
まだ年次の浅かった島﨑氏がクオリティの高いアプリを開発したことは、周囲の従業員にも波及していきます。使いやすいツールができたことで実際に業務が改善されるという成功体験を得て、「確かに便利になった」「自分にもできるかも」と、アプリ開発に興味を持つ従業員が少しずつ増えていきました。
メリットを感じられる体験と経営陣の後押しが成功要因に
同社のアプリ開発は、必要性を感じた従業員が自主的に行っていますが、効率的に開発を進めるためには、環境整備が重要だと島﨑氏は語ります。
「アプリ開発にあたる従業員にも通常の業務があるため、業務量の調整には周囲の理解が必要です。その点、当社は各部門長がIoT部門のメンバーであることや、部門長自身も開発にトライしていることなど、理解を得やすい環境だったことがプラスに働きました。また、開発には時間がかかりますが、例えば『この期間は開発に集中する』と決めて本業のウエイトを減らすことを可能にするなど、開発スピードを上げるための環境も構築しています」(島﨑氏)

画像②/難しい会計書の内容をイラスト化し、従業員にも分かりやすく表現した「風船会計アプリ」(図中の数字はダミー)
実際に、決算書を視覚的に表現し把握しやすくした「風船会計アプリ」(画像②参照)を開発したのは、普段は経理業務に従事する従業員で、元々はプログラミングの知識もなかったといいます。アプリには、貸借対照表や損益計算書がイラストで表現され、例えばイラスト内にある風船は売上額を意味し、その中には“重り”となる経費の金額が入っています。これにより、会計知識を持っていない従業員でも自社の経営状態を知り、「風船をより高く飛ばすには」と改善点を見つけ出すのにも役立てられています。
また、松本興産では賞与に「業務改善枠」を設け、アプリなどを活用した業務改善に貢献した従業員に対して賞与を配分する取り組みを始めました。業務改善や、そのためのアプリ開発がプラス評価の対象となることで、リスキリングやアプリ開発に対する従業員のモチベーションが高まっていると島﨑氏は言います。
「改善のタネはそこかしこにあります。例えば最近、業務改善枠で最も評価されたのは、社内のエアコンの稼働状況を一度にチェックでき、消し忘れを防ぐことで節電につなげるという非常にシンプルなアプリでした。誰かが『これがあれば便利だ』と感じたものをすぐに開発できる土台ができています」(島﨑氏)
島﨑氏は現在、工場管理業務と兼務して従業員のアプリ開発サポートにもあたるなど、松本興産のさらなる業務改善の推進役を担っています。今は棚卸集計のアプリ開発に着手しており、さらに非接触タグによる在庫管理自動化など、効率アップのためのさまざまな変革も思い描いていると言い、デジタル人材の育成と活用は今後も続いていきます。
- ※1 リスキリング
- 技術の革新やビジネスモデルの変化に応じて、新たな知識やスキルを習得すること。
- ※2 ローコード・ノーコード
- プログラミング言語の使用を減らしたり(ローコード)、全く使用しないこと(ノーコード)。

| 会社名 | 松本興産株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1970年(昭和45年) |
| 所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1 |
| 代表取締役 | 松本 直樹 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 事業内容 | 自動車部品をはじめ、医療機器や産業機械などに使用される金属部品の精密切削加工を行う |
| URL | https://mkknc.co.jp/ |
関連記事
-
![-東和組立株式会社-<br>身の丈 IoTで多様な人材を戦力化したダイバーシティ経営の秘訣]()
-
![-株式会社ミヤックス-<br>創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス]()
2024.10.25 公開
-株式会社ミヤックス-
創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス公園の遊具にセンサーやカメラを取り付けて業務のスリム化を模索する実証実験や、デー...
-
![-旭鉄工株式会社-<br>生産性向上、CO2削減まで成功した製造会社のDX戦略]()
-
![-社会福祉法人みなの福祉会-<br>人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減]()
2023.08.25 公開
-社会福祉法人みなの福祉会-
人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減緑豊かな埼玉県秩父郡皆野町で、老人福祉施設を運営する社会福祉法人みなの福祉会は、...
-
![-秋田酒類製造株式会社-<br>東北最大級の蔵元が挑戦するIoTと人の五感を活かした酒造り]()