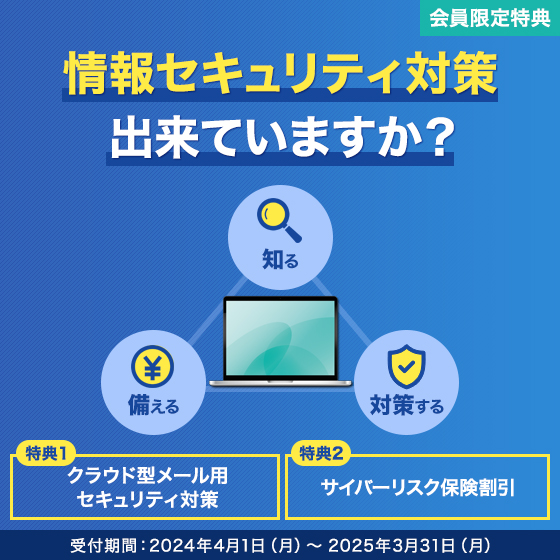企業ICT導入事例
-秋田酒類製造株式会社-東北最大級の蔵元が挑戦するIoTと人の五感を活かした酒造り
記事ID:D20022

秋田県を代表する東北最大級の蔵元・秋田酒類製造株式会社は、近年酒造りに欠かせない職人・
酒造りの実際の作業を担う蔵人の高齢化・減少が顕著に

生産本部 製造部
係長 倍賞 弘平氏
秋田酒類製造株式会社は国内でも有数の生産量を誇る酒造メーカーです。蔵には約200本の醸造タンクが建ち並び、「秋田流寒造り」と呼ばれる伝統の技で毎年美酒を醸かもし続けています。しかし近年、現場で酒造りに携わる蔵人の高齢化が顕著となり、「山内杜氏」の名で知られる、全国でも屈指の酒造り技術の継承が不安視されています。現在同社には約50名の蔵人が在籍していますが、そのうち半数は季節蔵人と呼ばれる外部の季節労働者です。季節蔵人の平均年齢は60歳前後であり、健康面での不安や担い手不足の問題は深刻で、同社は作業の省力化を進めるとともに蔵人のノウハウを次代に伝える必要性を感じていました。
「酒造りでは
発酵タンクの遠隔監視で蔵人の負担を削減
「2017年12月、秋田県産業技術センターからIoTの活用で業務の効率化と技術の可視化を図る提案をいただき、『発酵タンク温度の遠隔監視』と『もろみ成分の自動分析』に挑戦し、生産ラインを遠隔監視できるシステムの構築に踏み出しました。試験は、2018年の冬に小型タンク一本でスタートし、多数の温度センサーをタンクに挿入してもろみの温度分布を計測(写真①参照)したり、濃度センサーとタンクの重量センサー数値からもろみの発酵分析値(日本酒度※とアルコール度数)を推算する研究を繰り返しました。IoTに明るいとは言えず、通信ネットワークも未整備だった弊社にとって、プロとの協業は技術的にもイニシャルコストの抑制面でも大いに助けられました」(倍賞氏)

写真①:自動分析発酵タンクの右側の箱に収納されたマイコンからタンクの温度や重量が サーバーに送られ、現場に出なくても事務所で一括した監視が実現した。また、現在では数十分に1回の計測を行っているため、1日1回の計測だった従来に比べてきめ細かい温度管理ができるようになった
発酵タンクの温度管理(もろみの管理)は、酒の品質を左右する重要なプロセスです。蔵人はほぼ毎日もろみをサンプリングし、発酵値を分析した上で仕込み米や麹の種類、質、気温などの要素を検討して、一本一本最適な温度に調節しています。厳寒期の早朝から行われる大変厳しい作業です。
「このプロセスでIoTが活用できれば、蔵全体のタンクの温度監視やもろみの発酵度合いの推測が可能となり、蔵人の作業が軽減されるだけでなく、データベースの取得にも結びつくと考えました」と倍賞氏は言います。
「研究は2018年から3年間続けて実施し、2021年からは約50本の発酵タンクで、温度を遠隔監視するシステムを導入し、もろみの発酵度合いを自動で推測するタンク2基(コラム参照)を導入しています。これにより、事務所のパソコンだけでなく、蔵人個人のパソコンやスマホからもタンクの発酵状況が把握できるようになりました。このデータはほぼ常時更新されており、杜氏からも以前に比べより繊細な発酵管理が実現したと評価されています。特に若い蔵人たちの間ではスマホで常に状況を確認し、気になるとすぐに杜氏に相談することで自分自身の学びにもなっているようで、大いに手応えを感じています」(倍賞氏)
また、温度の遠隔監視システムは、麹造りにも活用されています。製麹の現場は麹の温度単位でさまざまな作業が発生するため、仕事時間は昼夜を問いません。これまで麹が目標温度に達したかどうかは現場で確認するしかなく、蔵人が何度も現場と寮の間を雪にまみれながら行き来する光景も珍しくありませんでした。しかし、今では最適な温度に到達したことを確認してから現場入りすればよくなり、特に夜間作業の効率化が進みました。
「将来的には、蒸米の工程にも温度遠隔監視を設置して計測を始めたいですね。またタンクにカメラを設置して表面の様子を撮影し、AI画像処理ができるようなシステムにも挑戦したいと考えています」(倍賞氏)
背伸びをしないIoT運用で技術を次代に伝えていく
IoTの有効性は実証されましたが、蔵人の中にはパソコンなどになじみのない人や小さな文字が苦手な人も多く、もろみの発酵管理の記録はこれまで通りの手書きでも行っているのが実情です。そのため、「現在得られた温度データやもろみ分析値は、主に遠隔監視やデータベース作成のために活用しています」と倍賞氏は語ります。
「IoT導入の最大のメリットは、年間1,000枚以上にかさんでいた発酵記録の自動化ですが、現在は時期尚早と考えています。発酵タンク温度の遠隔監視によって蔵人の温度管理のノウハウを可視化することはできましたが、もろみや麹といった発酵を伴う生産工程の判断基準は、分析値よりも見た目、手触り、香りといった人間の五感が重要だと改めて認識したからです。そのため、今は弊社の環境に適した背伸びをしないIoT運用が重要だと考えています」(倍賞氏)
現在は、蓄積されたデータの分析が進んでおり、「温度変化の平均値や振れ幅などの温度経過の分析から、長年培われてきた弊社独自の発酵管理の秘訣が見え始めています」と倍賞氏は話します。
「現在、IoT導入の最大の目的は、弊社の酒の味が生まれるプロセスをデジタル管理して、蔵人の技術を次の世代につなげていくことです。属人化されやすい蔵人の知恵の一端がデジタル化されつつあるのは大きな収穫で、これらの成果は、次代を担う蔵人たちの酒造りの技能習熟に、大いに役立つと考えています」(倍賞氏)
蔵人のスキルのように個人の五感、経験を頼りに生産を続けてきた企業はデジタル化が難しく感じられます。同社もすべてをデジタル化できなかったものの、温度や発酵度合いをデータ化して遠隔監視できるようにしたことで業務負担を軽減し、また技術伝承の一助として活用しようとしています。このような取り組みは、デジタル化は難しいと考える企業にとって大きなヒントになると思われます。
【コラム】もろみの発酵度合いの自動分析

もろみの濃度センサー(左)と、重量センサー(右)
もろみの発酵管理方法の一つに、日本酒度とアルコール度数の値を計測し、その値で発酵度合いを日々把握し、過去一番おいしくできた際の計測値を基準として、それに近づけるように温度管理する方法がある。そのために、これまではほぼ毎朝、多くのタンクからもろみのサンプルを採取、ろ過してから、日本酒度、アルコール度数を測定するという工程を行ってきたが、これがなかなか手間のかかる工程だった。そこで同社は、もろみの濃度センサーと重量センサーをタンクに設置、変化するもろみの糖度や重量を計測し、その計測値よりアルコール度数、日本酒度を自動で推算する技術を開発。推算値はリアルタイムで確認可能なため、これまで1~2日1回程度行っていた測定は、3 ~ 4日に1 回程度に減らすことができ、かなりの効率化と省力化を実現したという。
- ※ 日本酒度
- 甘口辛口を示す指標。
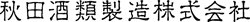
| 会社名 | 秋田酒類製造株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 1944年(昭和19年)8月 |
| 本社所在地 | 秋田県秋田市川元むつみ町4番12号 |
| 代表取締役社長 | 平川 順一 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 事業内容 | 厳選された秋田の米と水を使用し、秋田流寒造りの日本酒を生産する東北最大級の蔵元。焼酎、リキュール、化粧品も製造・販売している |
| URL | https://www.takashimizu.co.jp/ |
| 〔ユーザ協会会員〕 |
関連記事
-
![-松本興産株式会社-<br>自社開発のアプリで業務効率を大幅に向上 従業員の“デジタル人材化”を後押しする環境づくり]()
2025.04.25 公開
-松本興産株式会社-
自社開発のアプリで業務効率を大幅に向上 従業員の“デジタル人材化”を後押しする環境づくり松本興産株式会社は、自動車や精密機器などに使われる金属部品の切削加工メーカーです...
-
![-株式会社ミヤックス-<br>創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス]()
2024.10.25 公開
-株式会社ミヤックス-
創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス公園の遊具にセンサーやカメラを取り付けて業務のスリム化を模索する実証実験や、デー...
-
![-旭鉄工株式会社-<br>生産性向上、CO2削減まで成功した製造会社のDX戦略]()
-
![-社会福祉法人みなの福祉会-<br>人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減]()
2023.08.25 公開
-社会福祉法人みなの福祉会-
人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減緑豊かな埼玉県秩父郡皆野町で、老人福祉施設を運営する社会福祉法人みなの福祉会は、...
-
![-株式会社リョーワ-<br>事業環境の変化に合わせAIで新規ビジネスを創出]()