2016年 もしもし検定実施機関表彰
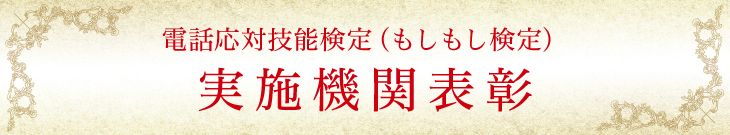
日本電信電話ユーザ協会では、毎年、電話応対技能検定の発展に貢献していただいた検定実施機関を表彰しており、2016年は下記の3項目について、5機関に感謝状を贈呈しました。(表彰対象期間は2015年10月~2016年10月)
表彰された各検定実施機関の代表者の方々に、もしもし検定に対する取り組みをお聞きしましたので、ご紹介します。
- ■1級~3級合計の受検者数
- 第1位:パナソニック株式会社
第2位:NTTソルコ&北海道テレマート株式会社 北海道事業部
- ■4級の受検者数
- 第1位:株式会社NSGコーポレーション
第2位:日本ハム株式会社
- ■1級~ 3級合計の合格率
(ただし、受検者数が50名を超える場合に限る) - 第1位:日本ハム株式会社
第2位:オフィスKEI株式会社
※日本ハム株式会社は、「4級の受検者数」と「1級~3級合計の合格率」の2項目を受賞。
パナソニック株式会社
-
![井上 一彦氏]()
▲総務部 部長 井上 一彦氏
-
![大森 康二氏]()
▲総務部 企画助成課 課長
大森 康二氏 -
![]()
接遇品質向上全社活動の社内浸透が、受検者増の要因
当社は2010年の検定実施機関登録以降、もしもし検定の受検者が右肩上がりに増えています。これはもしもし検定の内容がマナー教育に力を入れる当社のニーズに合致していることはもとより、「お客さま第一」という経営理念がさらに浸透し、接遇品質向上への理解が社内全体に広がったことが、受検者増の要因ではないかと考えています。また最近では、社内イントラネットを使ったこうした取り組みの発信や、約2,000名のマナーリーダーやインストラクターによる各職場での啓発活動により、各事業所の研修担当、応対品質担当からの問い合わせが増加し、もしもし検定の効果の口コミも広がりをみせています。
今後は「電話の向こうにいるのはすべてお客さま」という考えのもと、直接のお客さま応対部門だけでなく、パナソニックの全部門、全職種にこうした教育の裾野を広げていくことを計画しており、その過程で引き続きもしもし検定を活用させていただく所存です。
NTTソルコ&北海道テレマート株式会社 北海道事業部
-
![石田 良夫氏]()
▲常務取締役 北海道事業部長
石田 良夫氏 -
![菊地 義博氏]()
▲北海道事業部 事業推進部門長 菊地 義博氏
-
![]()
道内企業全体の電話応対品質向上への寄与を目指す
当北海道事業部は2016年10月にNTTソルコ&北海道テレマート株式会社の組織として新たな船出を迎えました。このもしもし検定は、旧北海道テレマート社時代に社内の指導者を育成するプログラムとして取り入れました。その後、社内の指導者級資格保持者の増加に伴い、社外の研修事業の受注拡大にも力を入れ始めました。
2016年はその社外研修事業の受注が前年に比べ増加しました。当社内に上位級資格取得者が多く在籍していることが、実施機関としての営業活動においてクライアントへの説明に説得力を与え、受注につながっていると考えています。
2016年の全国電話応対コンクールで当事業部から優勝者を出し、そのことを地元のテレビ局に取り上げていただくなど、当社の電話応対品質の高さを対外にPRができましたので、今後はさらに、もしもし検定実施機関として道内企業全体の電話応対品質向上に寄与してまいります。
日本ハム株式会社
-
![末澤 壽一氏]()
▲常務執行役員
代表取締役社長 末澤 壽一氏 -
![]()
-
![]()
ニッポンハムグループにもしもし検定の取得を推進
私たちメーカーにとって大事なことは、お客さまや社会とのつながりを大切にし、消費者ニーズを把握した上で商品開発などを行うことです。ニーズを把握し経営に活かす取り組みの一環として、毎年、私を含めグループの全役員、及び事業本部の幹部が電話受付のサービス部まで足を運んで、フリーダイヤルに入る「お客さまの声」を直接聴く活動を行っています。そして電話応対メンバーに限らず、全グループのスタッフにもしもし検定の取得を推進し、コミュニケーション力を向上させ、「お客さまの声」をより丁寧に聴けるよう努めています。
このような取り組みを一つひとつ積み上げていくことが、お客さまに選ばれ支持され続ける企業になることにつながっていくと考えています。
(2017年1月、日本ハム株式会社は、消費者庁が推進する消費者志向経営を実現するため、「消費者志向自主宣言」※をしました。)
消費者庁が推進する活動 http://www.caa.go.jp/
オフィスKEI株式会社
-
![田渕 惠子氏]()
▲代表取締役社長
田渕 惠子氏 -
![]()
-
![]()
希望者に対し、研修外での追加指導を実施
もしもし検定の研修は、「資格取得のためだけではなく、ビジネスやプライベートの場面でも活かしていける内容でなければならない」ということを弊社の基本的概念としています。それゆえに講義で学んだ知識を実践で活かすイメージを持ってもらいたいと考え、ロールプレイングやグループ討議などを研修に多く取り入れています。また希望者に対し、研修当日の時間外に2時間程度の追加の実技指導や1級受検者向けの小論文の書き方練習、そして研修終了後にも2問までの小論文の添削指導を、無償で行っています。
弊社では企業さま向けの研修のほかに、企業の垣根を越えて研修を受講できる公開セミナーを実施しています。受講後にも連絡を取り合う受講生もいて、こういった一体感や支え合う心を育む雰囲気も、各自の意欲向上につながり、合格率アップの背景となったのではと考えております。今年度も各級2回以上行う予定です。




































