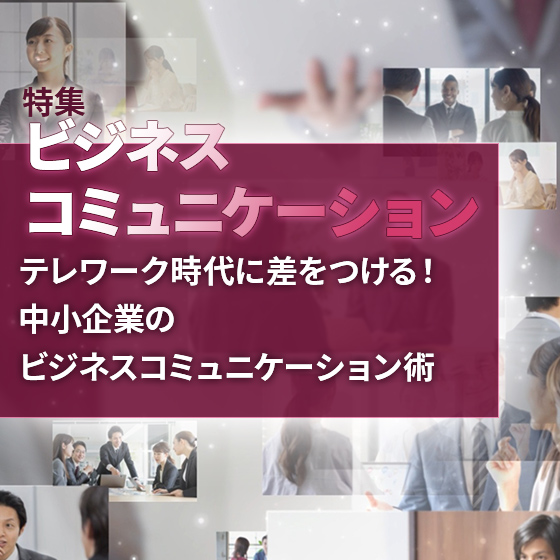電話応対でCS向上コラム
第136回 「大いなる『数』の力」記事ID:C10153
人類の長い歴史の中で、私たちの先祖は、数々の発明をしてきました。その発明の中でも、人類史に大きく寄与した発明の一つが、6000年前にメソポタミア地方に生息していたシュメール人が考え出した「数」という概念だと言われています。今回は、この「数」の力を辿ってみます。
人類の歴史と「数」
世界各地で行われている遺跡発掘調査では、傷のような線が刻まれた石や骨が見つかることがあるそうです。その一つに、シュメール人のくさび形文字の原形があるのでしょう。その数字はやがて1から9に育ちました。さらに、インドでは今につながるアラビア数字が生まれ、「0」の概念が人類の知恵をさらに高度に押し上げていったのです。
「万物は数なり」
この言葉を発したのは、古代ギリシャの有名な数学者ピタゴラス(紀元前572年頃生まれ)です。皆さんも、中学時代に習った「ピタゴラスの定理」(三平方の定理)をご記憶でしょう。ピタゴラスは、宇宙のあらゆる現象は、「数との調和によって成り立っている。この数の法則によって宇宙の真理は解き明かされる」と考えました。
数は暮らしの必需品
数に強い人がいる
たくさんの人とつき合ってきますと、信じられないほど数に強い人がいるのに驚きます。たくさんの買い物をしても、電卓など使わずにたちどころに合計金額を算出する人、会合などでの飲み食いの割り勘額などもさっと計算できる人がいます。こういう人は株の投機などにはきっと強いのでしょう。
かつて私の先輩に、鈴木 健二さんという昭和期のテレビの花形アナウンサーがいました。著作も多く、『気くばりのすすめ』という当時の大ベストセラーを出してからは、「気くばりおじさん」の愛称で、一世を風靡しました。その鈴木 健二アナが、数字に関して驚異的な記憶力をお持ちでした。番組の解説などに出てくる8桁ぐらいまでの数字ですと、一度目を通しただけで完璧に覚えてしまうのです。ただただ唖然として聴くばかりでした。
AIたちの数字力
今、私たちは、驚異的に進歩を続ける生成AIたちとの共生の時代にいます。そのAIたちの計算力は、おそらく想像を絶する域にあると思います。1956年にアメリカのダートマスで開かれたダートマス会議で、参加していたジョン・マッカーシーという計算機を専門とする学者がAI(Artificial Intelligence)人工知能という言葉を紹介したのがAI時代の幕開きと言われています。そこには、今後ともに数字とは因縁の深いAIの姿が垣間見えます。
「3」という数字
話を現実の対話の中で必要な数字の力に戻しましょう。洋の東西を問わず、古来、数字には、それぞれに意味があり、その魔力は占星術や数秘術として使われていますが、その世界とは別のところで、私が大事にしている数字があります。それは「3」です。
多様で多彩な表現力を持った日本語は、言葉を巧みに整理整頓することで、言葉を魅力的に分かりやすくしています。その整理整頓や統合に最も多く使われているのが、3点に分類する方法です。ぱっと思いつくだけでも大中小、上中下、天地人、松竹梅、三原色、金銀銅、雪月花などは、三つに分けることですっきりしますし、印象深くもなります。
また、三冠王、日本三景、三種の神器、三大名物、三大祭など、その町の歴史、観光、名物などはほとんどが「3」で括られています。「3」は具体的な数です。そして大きな可能性を秘めた数です。話は三つに整理して考え、伝えること。3点法が生きてきます。

岡部 達昭氏
日本電信電話ユーザ協会電話応対技能検定委員会検定委員。
NHK アナウンサー、(財)NHK 放送研修センター理事、日本語センター長を経て現在は企業、自治体の研修講演などを担当する。「心をつかむコミュニケーション」を基本に、言葉と非言語表現力の研究を行っている。