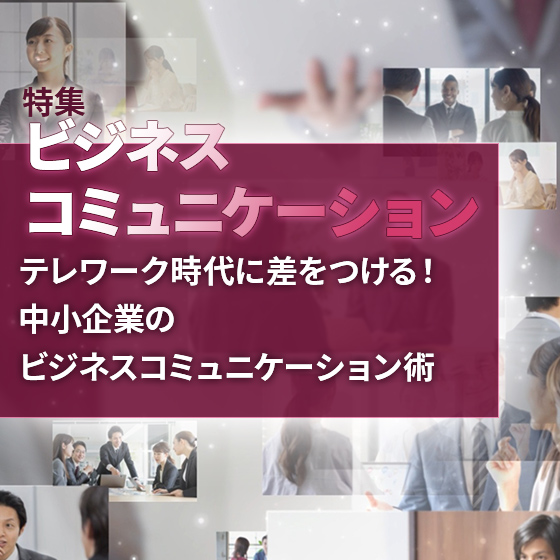電話応対でCS向上コラム
ハラスメント対策とは(後編)記事ID:C10151
前回に引き続き、ハラスメント対策について解説していきます。ハラスメントの判断は、時に紙一重です。叱責が適切な指導と受け止められるか、それともパワハラと評価されるか。その違いは言葉の選び方や態度にあります。判例を手がかりに、職場で実践できるポイントを考えてみましょう。
具体的な事例を考える
「パワーハラスメント」と聞くと、怒鳴り声や暴力的な場面を思い浮かべる方も多いでしょう。けれど実際には、それだけではありません。
法律上のパワハラとは、①優越的な立場を背景にした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③労働者の就業環境を害するもの。この三つがそろった時に成立します。
例えば、無視、実現困難なノルマ、逆に仕事を与えないといったことなども考えられます。企業にはパワハラを防止する責任があり、管理職は「自らやらない」ことだけでなく「起こらないような環境をつくる」ことも重要です。
一方で、最近は「パワハラを恐れて厳しく指導できない」「部下がパワハラだと主張して指示に従わない」という話もよく聞きます。
判例紹介
ここで実際の裁判例を見てみましょう。大裕事件(大阪地裁平成26年4月11日判決) では、部下が適応障害を発症し、休職に至ったケースが争われました。業務について大声で叱責した、その内容について、次のように判断が分かれました。
「何やってんの。何時間かかってんの」「そんなに時間がかかるものなんか」という叱責について、「時間がかかる」という事実の指摘で、適切とは言い難いものの違法ではないと判断。「あほでも分かる」「能力が劣っている」という叱責については、原告の能力が低いと原告の人格を否定するような内容であり、原告に与えた心理的負荷は大きく、パワハラであると判断されました。
パワハラと指導の境目
数多くの判例を見ていると、共通するのは「やりすぎかどうか」です。人格を否定する、皆の前で怒鳴る、何時間も説教を続ける。こうした行為は、本人は指導のつもりでもパワハラとされる可能性が高いのです。
ただし、部下の育成は上司の重要な責務です。優しく伝えても改善されないことは当然あります。そこで求められるのは、事実に基づき、冷静に改善策を提示する力です。「何が問題なのか」「なぜ改善が必要なのか」「次にどう行動するのか」を明確に伝える。必要に応じて書面に残す。こうした具体性のある対応が、パワハラではなく指導として受け止められます。
一方で、労働者には秩序維持義務がありますから、上司からの明確な指示には従わなければなりません。日常的には信頼関係を築きつつ、指導の場面では冷静かつ筋道の通った対応を心がける。その両立が管理職に求められています。
働きやすい職場について
実はパワハラは、訴訟になれば会社側の言い分が通ることもあります。しかし大切なのは、訴訟で勝つかどうかではありません。ハラスメントに当たらなくても、威圧的な態度やコミュニケーション不足から誤解が生じるなどで、「ハラスメントを受けた」と思われてしまうケースは多いでしょう。それは厳密にはハラスメントではないかもしれませんが、従業員のモチベーション低下や離職、メンタル不調を招くことは確かです。
ここで注目されるのが「心理的安全性」です。誰もが安心して意見を言える職場は、ハラスメントの芽を早期に摘むだけでなく、若手からの発言も活発になり、組織力を高めます。相談窓口や対応マニュアルも大切ですが、最も有効なのは心理的安全性を備えた風土づくりなのです。
最後のまとめとご挨拶
これまで、本連載にて12回にわたり労務管理の基本をお届けしてきました。根底にあるのは、「働くことは労使が対等に結ぶ契約関係である」ということ。そして、労働法は労働者を守るためだけでなく、企業の規範を整え、信頼される職場をつくる基盤でもあるということです。
ただし、法律を守るだけでは足りません。人と人との関係である以上、日々のコミュニケーションも重要です。仕組みと心、その両方を大切にすることで、納得のある労使関係と、働きがいのある日常が生まれます。
この連載が、皆さまの現場での実践に役立ち、安心して働ける職場づくりにつながれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。