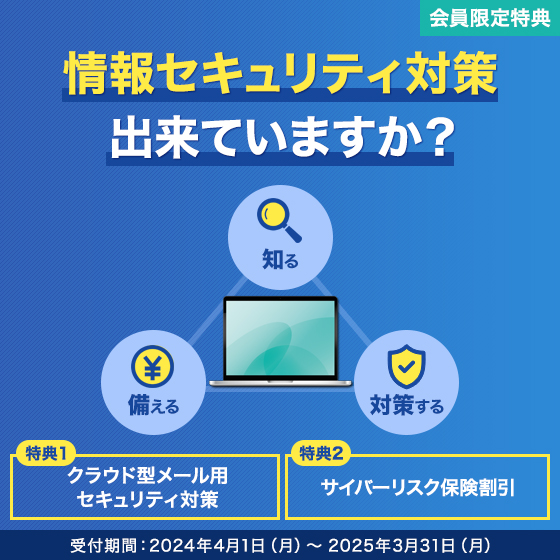企業ICT導入事例
-福岡市役所-福岡が誇る観光資源屋台文化を守った「屋台DX」とは
記事ID:D20038

九州・福岡市は全国有数の屋台密集地域であり、屋台は同市を代表する観光資源でもあります。観光客だけではなく、市民の憩いの場でもある屋台ですが、かつて存続が危ぶまれていたことがありました。今回は、ICTを駆使して屋台の復活をサポートした福岡市の「屋台DX」について、福岡市役所の山喜多 洋一氏に話をうかがいました。
福岡の屋台文化を残すべく「屋台基本条例」を施行

経済観光文化局
文化まつり振興部
屋台課 屋台係長
山喜多 洋一氏
福岡市には現在98軒(2025年3月末現在)の屋台があり、年間約120万人もの利用者がありますが、かつては消滅の危機を迎えていたと、福岡市役所の山喜多 洋一氏は語ります。
「屋台は戦後の闇市から始まり、これまで何度か廃止の危機がありました。道路や公園などで営業することから、深夜の騒音や悪臭などの問題が発生し、福岡県警の方針により一度は屋台を廃止しようという流れになりました。しかし、屋台は福岡市の重要な文化であり、存続させるべきだということで、市は2013年に『福岡市屋台基本条例』を施行し、近隣住民にも受け入れられるよう、占用時間や屋台規格などの守るべきルールを定め、上下水道などの環境整備も実施しました」(山喜多氏)
条例を施行することで屋台文化は守られた結果、約100軒もの屋台が維持され、全国でも珍しい存在となり、福岡の評価を高める一因にもなっています。一方で、福岡市には長浜、天神、中洲の三つの屋台街がありますが、長浜エリアは店主の高齢化や人流の変化などにより、軒数が激減して存続の危機を迎えていました。この長浜を復活させる起爆剤となったのが「屋台DX」だったと、山喜多氏は当時を振り返ります。
「一時は15軒が軒を連ねていた長浜は、2021年には2軒まで減少し、そのうち1軒も休業中という状況でした。しかし、2022年に実施した公募で新たに7軒の出店が決まり、2023年6月には長浜屋台街として復活を遂げました。その長浜屋台街を盛り上げるため『屋台DX』に取り組みました」(山喜多氏)
営業状況がスマホで分かる「屋台DX」を導入

写真①:IoT電球を灯すと、SIMから「営業中」という情報が送信され、LINEアカウントに反映される仕組みになっている
屋台DXで最初に取り組んだのは、営業状況の見える化でした。屋台は日中、何もない公園や道路に毎日設営して営業するため、荒天時には休業となることがあり、営業しているかどうか現地に行かないと分からないという課題がありました。とりわけ長浜は、繫華街から少し離れたところに位置しているため、足を運びづらい状況でした。
「この課題を解決するため、2023年6月に屋台のLINE公式アカウント『FUKUOKA GUIDE』を開設し、屋台の営業状況が分かる仕組みを導入しました。IoT機器を屋台に設置して、電源を入れてもらうことで、営業開始を知らせるというものでした。これにより利用者の利便性が高まり、LINE公式アカウントを見て来たという観光客も増えました」(山喜多氏)
さらに、当時は混雑状況の見える化にも取り組み、1軒で試験的にAIカメラを導入し、お客さまの出入りをチェックしていました。しかし、屋台ははしごをしながら飲み歩くことが多いため、利用者の回転率が高く、さらにトイレで席を外しただけでAIが空席と判断してしまうなど、リアルタイムで実態を表示することが難しいという課題がありました。そのため現在、混雑状況の見える化は行われていません。
屋台DXの進化版としてIoT電球、生成AIを導入

写真②:現在地やエリア、グルメ(食べたいメニュー)などの条件からおすすめの屋台を検索でき、「AIおいちゃん」に直接リクエストを伝えることも可能
長浜エリアで実施した営業状況の見える化は好評を得て、2024年7月には天神や中洲エリアにも導入され、福岡市内の約1 0 0軒の全屋台で展開されました。その際、営業状況を通知する仕組みも見直したと、山喜多氏は語ります。
「スペースが限られた屋台に、端末を置いてもらうのは負担になりますし、電源を入れるという別作業も発生してしまいます。そこで、端末を高齢者の見守りなどでも使われているSIM※を搭載したIoT電球に切り替えました(写真①参照)。電球ならばどの屋台でも使用していますし、電球を灯すという行為は開店準備の作業に組み込まれていますので、負担がないと考えました。おかげで、営業状況の見える化はほぼ100%となっています」(山喜多氏)
屋台には営業状況の見える化のほか、もう一つ大きな課題があり、その課題解消のため、IoT電球導入と同時に生成AIを搭載したチャットボット「AIおいちゃん」も実装されました。
「屋台には店主や隣り合う初対面のお客さまたちによるコミュニケーションという、大きな魅力があります。10席程度の特別な空間で同じ時間を過ごすと、自然に会話も弾んで仲良くなるという光景がよく見られます。そのため、自分の趣味や好みに合った屋台に行きたいけれど、どの屋台に行けば良いのか分からないという声もありました。そこで、約100軒の屋台から、利用者の条件に合った屋台を博多弁で案内する『AIおいちゃん』を開発しました」(山喜多氏)
「AIおいちゃん」はメニューや店主のパーソナリティまで学習しており、チャットの質問に応じて、屋台の看板メニューや店主のキャラクターまで、さまざまな情報を提供してくれます(写真②参照)。ちなみにチャットの質問で一番多いのは、メニューに関するものだと言います。
「質問は、やはり食べ物に関するものが多いですね。例えば、福岡が発祥とされていて、福岡屋台の名物とも言われている人気メニューに焼きラーメンというものがあります。福岡に観光や出張で来られた方が、『焼きラーメンのおいしい屋台はどこですか?』とチャットで質問をすると、AIおいちゃんは瞬時におすすめの屋台を教えてくれて、場所や営業時間、店内の雰囲気まで知ることができます」(山喜多氏)
今後も目指すべきはデジタルとアナログの両輪
A Iおいちゃんは、市役所がこれまでに蓄積してきた情報や、個別の取材情報を基に開発されました。
「取材では看板メニューなどはもちろん、店主の人柄も重要ですので『出身はどちらですか、趣味は何ですか』といったことまでお聞きしました。そうすると、『昔はスポーツに熱中していて国体にも出場していた』など、ユニークな情報まで出てきました。そのため、例えば『サッカーや野球が語れる屋台』などの情報も提供できるようになっています」(山喜多氏)
屋台DX を拡大させた結果、2024年7月から半年でLINEの友だち数は1万人以上増加し、3万5千人(2/21現在)を数えるなど、大きな成果を得ています。今後の戦略について、山喜多氏は次のように語ります。
「屋台にはアナログならではの魅力もありますので、それを意識したDXを考えるべきだと考えています。例えばモバイルオーダーなどは、店主とのコミュニケーションが魅力の屋台には不向きだと思います。そういう部分には考慮しつつ、便利になるものは積極的に取り入れたいと考えています」(山喜多氏)
屋台に必須の電球とIoT電球とを結びつけて、店主の負担にならないICT化を実現したり、お客さまが欲しい情報を入手できるようAIに学習させたり、屋台の特性を考慮してDX推進の方向を定めるなど、利用者側に立った「屋台DX」は、屋台という特殊なケースですが、多くの企業が参考にできる事例ではないでしょうか。
- ※ SIM
- Subscriber Identity Moduleの頭文字をとって「シム」と呼ばれ、日本語では「加入者識別モジュール」という意味で、スマートフォンやIoTデバイスに搭載するためにカードやチップといった形態で提供される。SIMには固有のID(番号)が付与されており、加入者を特定するための契約者情報が記録されている。

| 組織名 | 福岡市役所 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-8-1 |
| 市長 | 高島 宗一郎 |
| URL | https://www.city.fukuoka.lg.jp/ |
関連記事
-
![-株式会社ヤマト屋-<br>創業130年の老舗がSNSで挑む若年層の顧客開拓とICT活用による業務改善]()
2025.05.26 公開
-株式会社ヤマト屋-
創業130年の老舗がSNSで挑む若年層の顧客開拓とICT活用による業務改善創業130年を超える女性用バッグの老舗が展開する、SNSのユニークな活用法が注目...
-
![-株式会社デリシア-<br>地域密着型で取り組む長野県のネットスーパーの挑戦]()
-
![-株式会社九州パール紙工-<br>都市圏のプロ人材の経験を、地元の若手へ継承 外部人材を活用した地方企業の成長戦略]()
2024.06.25 公開
-株式会社九州パール紙工-
都市圏のプロ人材の経験を、地元の若手へ継承 外部人材を活用した地方企業の成長戦略少子高齢化による労働人口の減少に伴い、地方の中小企業のデジタル人材の確保はより困...
-
![-湯本電機株式会社-<br>メタバース参入で町工場が得た人材育成と新ビジネスのヒント]()
-
![-株式会社福しん-<br>創業理念「お客さまの声を聞く」を重視したネット時代の口コミマーケティング]()
2023.11.27 公開
-株式会社福しん-
創業理念「お客さまの声を聞く」を重視したネット時代の口コミマーケティング東京・池袋を拠点に首都圏で31店舗を展開するラーメン・定食の中華チェーン「福しん...