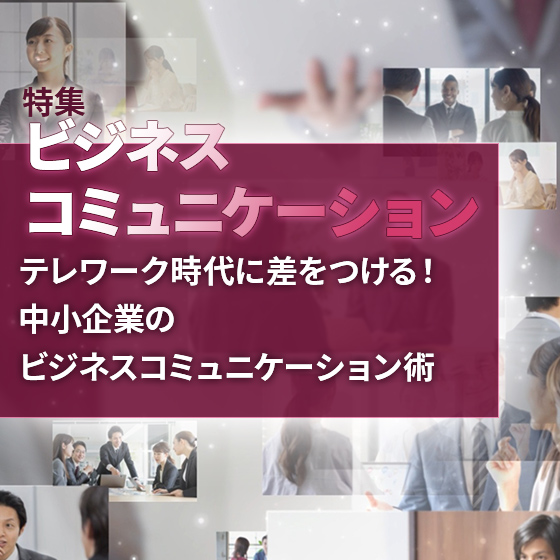ICTコラム
フェムテックの導入ポイントと将来性記事ID:D40063

女性の健康課題をテクノロジーの力で解決する商品やサービスであるフェムテックは、企業が従業員の健康維持や生産性向上を図る上で、重要なツールとして注目されています。最終回の本記事では、企業がフェムテックを導入する際の課題や成功のポイント、さらに将来性について解説します。
企業がフェムテックを導入する際の課題
フェムテック導入に際して、多くの企業が直面するのは「理解の壁」です。特に決定権を持つ経営層に女性が少ない場合、女性の健康課題についてなかなか理解が得られない、理解があったとしても、フェムテックを取り入れることによるメリットや、その効果を十分に理解してもらうことが難しいといった課題が挙げられます。
また、経営層に女性がいたとしても、自身の経験に基づき「生理痛をほとんど感じない」「女性特有の健康課題を実感したことがない」といった理由から「自分ごと」として捉えられず、導入に対して積極的ではないケースも多く挙げられている印象です。特に中小企業では、健康経営やダイバーシティへの取り組みが売上に直結しないとの認識が強く、優先順位が低くなる傾向があります。リソース不足や予算の制約がある企業ほど、健康課題に取り組むことが「コスト」と見なされ、積極的な投資が難しい場合もあります。
また、東京や大阪、福岡などのような大都市に比べて、地方では「なぜ女性の活躍が必要なのか」という健康経営の基本的な考え方がまだまだ浸透しておらず、フェムテック導入までの環境が整っていないケースも少なくありません。男性の育児休暇や女性の健康支援に関する取り組みが進んでいない地域では、フェムテックに対する関心が、東京などの都市部に比べて5年から10年遅れているという現状もあります。
フェムテックを上手に導入するためのポイント
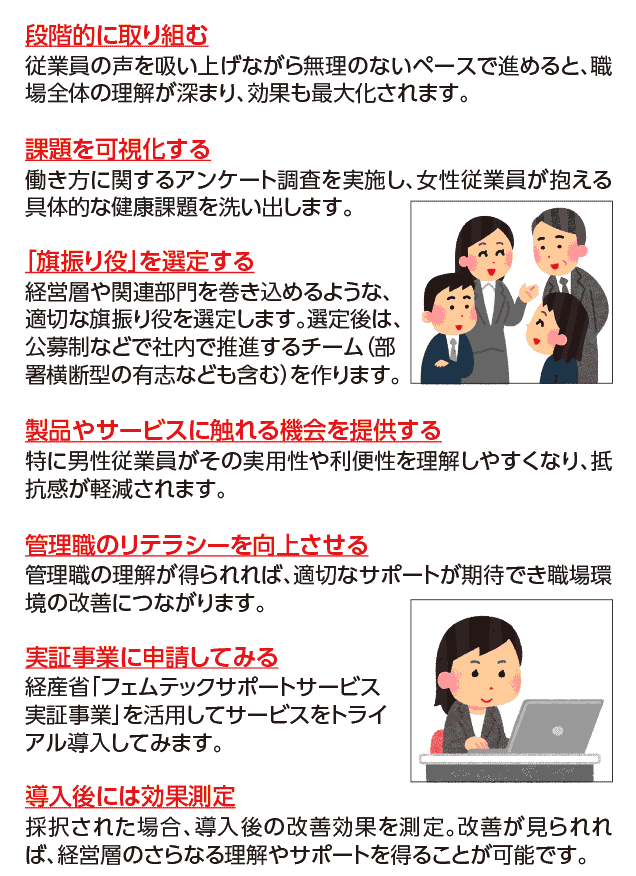
図:企業へのフェムテック導入のポイント
フェムテックの導入は、一度にすべてを進めるのではなく、段階的に取り組むことが鍵です(図参照)。従業員の声を吸い上げながら、無理のないペースで進めることで、職場全体の理解が深まり、導入の効果が最大化されます。
まずは、企業内での課題を可視化することが重要です。働き方に関するアンケート調査を実施し、女性従業員が抱える具体的な健康課題を洗い出します。例えば、「生理休暇を取りたいが取りづらい」「更年期の症状で仕事がつらいが相談できない」などの声を数値化することで、経営層も健康課題を認識しやすくなります。こうしたプロセスを通じて、健康課題が従業員の欠勤や離職につながっている可能性に気づき、経営層が問題を解決すべき課題として捉えやすくなります。
また、フェムテック導入には「旗振り役」の存在が欠かせません。この役割を担うのは、必ずしも女性である必要はありませんが、労働組合の女性メンバーは企業をより良くしようとする立場にあるため、推進役として非常に効果的です。女性従業員が直接声を上げにくい状況でも、労働組合のメンバーが課題意識を持ち、経営層や関連部門を巻き込むことで、導入プロセスがスムーズに進む事例があります。
加えて、フェムテック製品やサービスを実際に見たり、触れたりする機会を提供するのも効果的です。例えば、吸水ショーツや月経カップなどの製品に直接触れることで、特に男性従業員がその実用性や利便性を理解しやすくなります。こうした体験を通じて、フェムテックへの理解が進み、導入に対する抵抗感が軽減されるでしょう。
導入を進めるにあたり、管理職の健康リテラシーを向上させることも重要です。管理職が女性の健康課題を理解すれば、チーム内で適切なサポートができ、職場環境の改善につながります。一方で、健康課題に理解のない管理職の存在は、不適切な対応がパワハラやセクハラの問題に発展するリスクもあるため、最低限の知識を身につける機会を設けることが必要です。
さらに、経済産業省が実施する「フェムテックサポートサービス実証事業」を活用するのも有効な手段です。この実証事業では、サービス提供企業が自治体や企業と連携し、実験を行う形式が採用されており、企業はトライアル導入を通じて自社に適したサービスを選定できます。
フェムテック導入後には効果測定を行い、職場環境や従業員の健康がどのように改善されたかを数値で示すことが求められます。この取り組みによって、経営層のさらなる理解を得られるでしょう。
フェムテックの将来性
今後、より多くのフェムテック製品やサービスが登場すれば、女性は自分に合った製品を選択しやすくなり、健康課題に適したケアが受けられる環境が整います。これにより、未病ケアや日々の生活の質(QOL)向上、ウェルビーイング※なライフスタイルの実現につながるでしょう。
健康管理の充実は、女性がキャリアを継続しやすくなるだけでなく、自己実現の機会を広げます。健康課題を理由にキャリアを中断していた女性に新たな選択肢が生まれ、社会全体で女性活躍がさらに推進されると期待されます。
フェムテックの普及は、企業にとっても大きな意義を持ちます。フェムテックを活用して女性の活躍が進むことで女性管理職や役員が増え、多様な意見が取り入れられることによって、組織の柔軟性や競争力が高まります。
さらに、女性従業員の健康課題を解決する取り組みは、離職率の低下や生産性の向上を促し、企業全体のパフォーマンスを高める要素の一つでもあります。これらの取り組みは、企業のブランドイメージの向上にも寄与し、採用活動や従業員のモチベーションアップにも好影響を与えるでしょう。
日本ではフェムテック市場の発展が欧米に比べて遅れていますが、科学的根拠に基づく新たな製品やサービスが日本で開発され市場に広がれば、女性特有の健康課題に対応する選択肢がさらに増えるだけでなく、日本の緻密で丁寧な対応や製品開発が海外市場で評価される可能性もあり、グローバルでの展開による経済効果も期待されます。
市場が成熟するにつれ、より多くの女性が健康とキャリアを両立できる環境が整い、社会全体での女性活躍が促進されるとともに、企業や経済の発展につながっていくでしょう。
- ※ ウェルビーイング
- well(良い)とbeing(状態)からなる、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

株式会社シルキースタイル代表取締役CEO、一般社団法人日本フェムテック協会代表理事。大手下着メーカーで企画・開発を担当後、世界初の下着コンシェルジュとして独立。女性の体と下着の専門家として、インナー、コスメ、健康雑貨の商品企画開発を17年間行い、女性特有の健康課題に寄り添う活動を推進。2021年、日本フェムテック協会を設立し、ウィメンズヘルスリテラシーの重要性を発信。2児の母。
関連記事
- 電話応対でCS向上コラム(343)
- 電話応対でCS向上事例(279)
- ICTコラム(134)
- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)
- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)
- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)
- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)
- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)
- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(3)
- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)
- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)
- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)
- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)
- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)
- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)
- メタバースのビジネス活用(3)
- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)
- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)
- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)
- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)
- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)
- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)
- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)
- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)
- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)
- 子どものインターネットリスクについて(3)
- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)
- Z世代のICT事情(3)
- 企業ICT導入事例(187)
- ICTソリューション紹介(96)