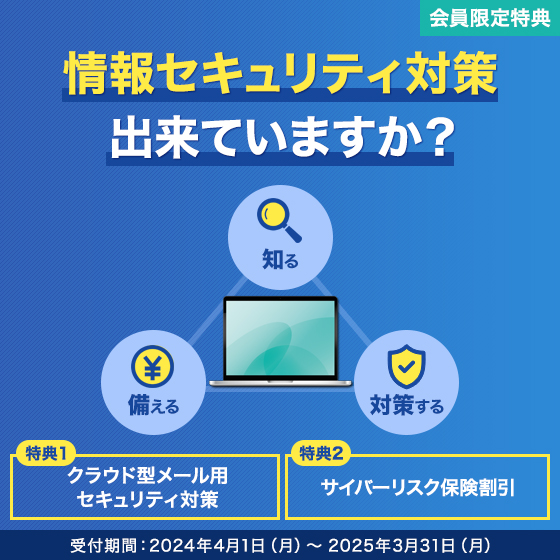企業ICT導入事例
-東和組立株式会社-身の丈 IoTで多様な人材を戦力化したダイバーシティ経営の秘訣
記事ID:D20045

労働生産性の向上や企業の社会的責任遂行のために、外国籍労働者や障がい者の受け入れに積極的に取り組む企業が増えています。IoTやAI技術を有効活用したダイバーシティ経営の推進で多様な人々を戦力化し、業績の向上に結びつけている東和組立株式会社代表取締役社長の林 佳寿彦氏に、「身の丈」に合ったIoT活用の重要性と、ダイバーシティ経営を実践するためのノウハウについてうかがいました。
赤字転落で五里霧中の中見える化改革を始動

代表取締役社長 林 佳寿彦氏
岐阜県美濃加茂市の東和組立株式会社は、主に自動車用油圧緩衝部品(ショックアブソーバー)の組み立てから梱包、出荷までの一貫生産を行う、地域密着型の企業です。美濃加茂市は製造業が盛んな土地柄で、20世紀末の入管法改正以来、ブラジルやフィリピン国籍を中心とする外国人住民を積極的に受け入れてきました。
美濃加茂市がまとめた「外国人住民国籍別集計表」によると、2025年9月現在、フィリピン人が2,679人、ブラジル人の2,167人を筆頭に、全人口約57,500人の約11%強にあたる6,390人の外国人が「永住者」「定住者」などの在留資格を持ち、同市で製造業などに従事しています。
「弊社も従業員の約33%が外国籍を有する、国際色豊かな企業です。また、地域社会への貢献のため、長年障がいのある人の採用にも取り組んでいます。現在、知的・精神・聴覚各障がい者を中心に18人を正社員として雇用しており、直接雇用率は厚生労働省が定める法定雇用率の約9倍となっています」(林氏)
こうした取り組みが評価され、同社は経済産業省の2021年度「新・ダイバ ーシティ経営企業100選」や、岐阜県の「ぎふSDGs推進ゴールドパートナー」に認定されました。しかし、以前の同社は不安定な経営状況に悩んでいたと、林氏は振り返ります。
「弊社は人件費などの固定費の比率が高く、顧客からの受注量の不安定化や納期期限の短縮などへの対応で、業績が悪化しやすい欠点を抱えていました。対応は後手に回りがちで、創業50周年を控えた2018年には、初めて赤字を計上しました。当時は経営力強化のために、業務の効率化と生産性の向上が喫緊の課題となっていましたが、現実的には赤字を生み出した問題点が見えていないため、何をどう改善すればいいのかも分からない、五里霧中の状況に陥ってしまいました」(林氏)
そこで同社は、これまで見えていなかった問題点を明確に「見える化」し、適切な判断力を養うために、会社の風土や従業員意識の改善に取り組みました。毎月全社集会を開催し、経営状況や採算分岐点などの数字、工程の進捗状況や稼働率などの情報を共有し、「『できない』『無理!』をなくすこと」を活動テーマに定め、社内の改善意識の醸成に努めました。
身近なツールを駆使した「身の丈IoT」を導入
問題点を「見える化」するために林氏が注目したのが、IoTの活用でした。美濃商工会議所が主催した、公益財団法人ソフトピアジャパンによる「身の丈IoT、目からウロコの12連発」という講演会で紹介されたIoTによる業務改善事例に、林氏は大いに触発されたと言います。
「中でも、手話つき動画で作成した作業マニュアルをクラウド上にアップし、従業員がいつでもどこでも見られるようにした改善事例などは、人手不足でなかなか技術教育に時間が割けない弊社が、すぐにでも採用すべきアイデアだと思いました。また、経営財源に限りがある中小企業には、いきなり高額なシステムを導入する体力はないだけに、低コストで従業員の手作りによる改善を提唱する『身の丈IoT』は、弊社のスタイルに適していると判断しました」(林氏)
改善の第一歩はウェブカメラの導入でした。機械組み立てから塗装、梱包、出荷まで、同社の製作工程は長く複雑なため、工程の一括管理に苦労していました。そこで林氏は、市販されている安価なウェブカメラを購入し、工場の各工程に設置して工場内の状況が同時に見られる仕組みを構築しました。これにより工程の遅れや在庫の多寡などが一目で把握できるようになり、素早い対応による生産性の向上に結びつきました。
「『みる』行為には段階があります。画像として認識する『見る』、注目する『視る』、関心を持って観察する『観る』、状況を診断する『診る』など、見る者の意識や情報量によって対応は変わります。情報の『見える化』により、従業員がより高度な『みる』意識を養うことで、作業の高度化や効率化が進み、業務改善に結びつくことを期待したのです」(林氏)
このほか、現場にはさまざまな「身の丈IoT」ツールが導入されました。例えば、現場に応援要請をする際、工場内は広大な上、騒音で声が伝わりにくいため、その都度、従業員が連絡に行き来する手間が発生していました。そこで、呼び出されていることが一目で分かるようにしたいと考え、市販の点滅式の防犯グッズやフードコートの呼び出しベルを設置しました。
また、無料ソフトを活用した全従業員のスケジュール管理の仕組みを導入することで、これまでホワイトボードのある場所まで出向いて確認していた従業員全員の予定や欠勤情報などが、パソコン上で即座に把握できるようにしています。
障がい、国籍を超えたダイバーシティ経営を実現

画像①: 今やるべき作業内容が一目瞭然で示される
改善の目は、外国人や障がいのある従業員にも向けられました。これまで外国人や障がいのある従業員の業務は、外部とのコミュニケーションが少ない「補助的な仕事」に限定されていました。しかし、さらなる生産性の向上には、彼らの戦力アップが欠かせません。そこでIoTによる業務の効率化と、新たな業務の創出が行われました。
「知的障がい者は、時間の観念が薄かったり別のことに気を取られたりして、気持ちが仕事から離れてしまう傾向が見られます。そのため業務の進行に支障をきたし、上司がその度に現場に足を運んで指導する時間のロスと手間が発生していました。そこでタイマーと連動した作業指示ランプを常設し、時間ごとに『入庫部品のかたづけ』『設備清掃と日常点検』などの指示を視覚的に伝達することで確実性が増し、サポートする側の時間的負担も軽減されました(画像①参照)」(林氏)
聴覚障がい者とのコミュニケーションには、音声を文字に変換してくれるアプリを活用しています。変換の精度や速度も許容できるレベルに達しているため、以前の筆談に比べて短時間で正確な意思伝達を可能にしています。国籍が複数にわたる外国人従業員については、音声変換ソフトを導入しているほか、毎月1回、生成AIの翻訳ソフトによる日本語、英語、ポルトガル語の3ヵ国語全体集会を実施し、インクルージョン※意識の醸成に努めています。また作業教育支援ツールとして、手話つきの各作業マニュアル動画を作成し、24時間検索可能な環境を整えました。このマニュアルは、障がい者の技量向上に役立つと同時に、同社の技術を伝える貴重なアーカイブになっています。

画像②: 規格に満たない場合は赤ランプが灯り作業者に知らせる
このほか、大きな成果を出しているのが、製品検査に使う画像診断機の導入でした。製品検査は、製品の形状や寸法、表面処理などの品質を最終確認する、大変重要な工程です。従来は熟練者に限られた特別な指名性業務でしたが、同診断機の導入により誰でも簡単に正確な判定ができるようになりました(画像②参照)。
「画像診断機はセンサーに部品を読ませるだけで、ピクセル単位で誤差を感知します。品質に問題がなければ青、NGの場合は赤ランプが灯り、判定結果を即座に知らせるとともにエビデンスを記録します。これにより、熟練者に限られていた職域が障がいのある従業員などの未熟練者にまで広がり、職域拡大と工場全体の業務能力が向上しました。改善前と比べて、モデルラインの生産性は約25%アップしています」(林氏)
現在、同社のダイバーシティ経営は大きく進展し、今ではブラジル人のチーム長が生まれ、フィリピン人のSEが誕生するなど、新戦力が続々誕生しています。障がいのある従業員の入社1年後の定着率 は、改善前 の 60%から90%に上昇しています。このような同社の取り組みは、人手不足に悩む中小企業にとって、大きなヒントになりそうです。

| 会社名 | 東和組立株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1969年(昭和44年)4月 |
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市川合町4-5-2 |
| 代表取締役社長 | 林 佳寿彦 |
| 従業員数 | 146名 |
| 事業内容 | 自動車部品の組立、塗装、梱包 |
| URL | https://towakumi.co.jp/ |
関連記事
-
![-松本興産株式会社-<br>自社開発のアプリで業務効率を大幅に向上 従業員の“デジタル人材化”を後押しする環境づくり]()
2025.04.25 公開
-松本興産株式会社-
自社開発のアプリで業務効率を大幅に向上 従業員の“デジタル人材化”を後押しする環境づくり松本興産株式会社は、自動車や精密機器などに使われる金属部品の切削加工メーカーです...
-
![-株式会社ミヤックス-<br>創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス]()
2024.10.25 公開
-株式会社ミヤックス-
創業75年の老舗がデジタル化で取り組む産官学と協働した地域貢献ビジネス公園の遊具にセンサーやカメラを取り付けて業務のスリム化を模索する実証実験や、デー...
-
![-旭鉄工株式会社-<br>生産性向上、CO2削減まで成功した製造会社のDX戦略]()
-
![-社会福祉法人みなの福祉会-<br>人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減]()
2023.08.25 公開
-社会福祉法人みなの福祉会-
人手不足時代の頼れる救世主 ロボット&ICTによる介護の質向上と職員の負担軽減緑豊かな埼玉県秩父郡皆野町で、老人福祉施設を運営する社会福祉法人みなの福祉会は、...
-
![-秋田酒類製造株式会社-<br>東北最大級の蔵元が挑戦するIoTと人の五感を活かした酒造り]()