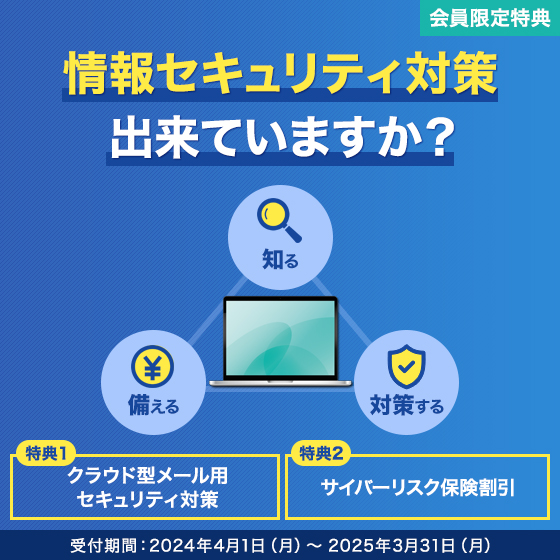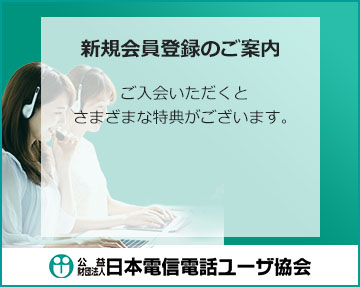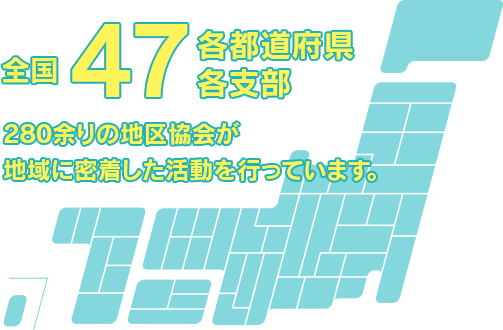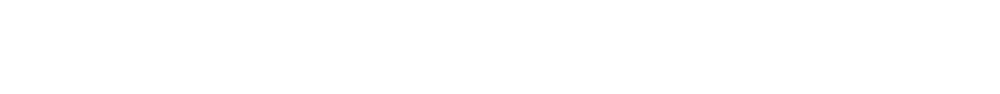ICTソリューション紹介
-みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社-2026年、注目のキーワードでビジネスシーンを読み解く
記事ID:D10059

人手不足の解消や新たなビジネスシーンの創出など、2026年もビジネス環境の改善や課題の克服のため、ICTの活用がますます深化していきそうです。そこで今回は、2026年に注目したいICTキーワードとして、「空間コンピューティング」「スマートロボット」、そして目覚ましく進化する「AI」に着目しました。デジタル技術が社会に与える影響などの調査研究を進める、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社デジタルコンサルティング部の西村 和真氏と木村 俊介氏に、各キーワードの現状と可能性についてうかがいました。
課題解消に期待される3つのICTキーワード
総務省は令和7年版情報通信白書の「ICT市場の動向」で、2025年度の世界ICT市場(支出額)は約5.44兆ドルに達すると予測しています。毎年10%近い成長曲線を描いており、競争力の強化に注力する企業からの需要がいかに高いかを示唆しています。また、同省は2025年8月次の労働力人口を7,017万人と発表しましたが、独立行政法人労働政策研究・研修機構は、2040年の労働力人口が最低の場合6,002万人になると予測しています。
このように年々深刻化する労働力不足を背景に、現在でも多くの業種でデジタル技術の導入が進められています。中でも「空間コンピューティング」や「スマートロボット」、「AI」は、業務の効率化や労働力不足の解消に資するツールとして注目を集めています。そこで今回は、それぞれの現状や今後の可能性について探りました。
キーワード①:空間コンピューティング
空間コンピューティングのビジネス活用が加速

デジタルコンサルティング部
政策・技術戦略チーム
課長 西村 和真氏
「空間コンピューティング」は、360度3DフルCG映像やゴーグルを活用して、今まで見えなかった、気づけなかった新たな体験を可能にする、デジタル空間と現実世界を融合させる技術です。自分がその世界に存在しているかのような没入感が味わえるVR(仮想現実)、現実空間にデジタル情報を視覚的に融合し、新たな情報を生み出すAR(拡張現実)やMR(複合現実)などの技術で構成されており、近年はこれらの技術のビジネス活用が広まっています。
西村氏:空間コンピューティングが注目される最大の理由は、ユーザーにかつてない新鮮な体験価値を提供できる機能性にあります。プロジェクションマッピングも一種の空間コンピューティングですが、ライブ感あふれた圧倒的な映像体験が熱烈な支持を獲得し、イベントでの活用など、新たなビジネス需要が生まれたのは記憶に新しいところです。また人手不足の課題解決にも有効です。例えばインバウンドにわく観光地では外国語のガイドが欠かせませんが、需要に対して人材が足りていないのが現実です。そこで人の代わりにARやMRを用いたガイダンスが登場し、人手不足の解消に貢献しています。
ほかにも、各分野で空間コンピューティングの導入が広まっています。建設業界では、建築物の全体像を外からは見られない配管構造まで完全に再現した3Dモデルを作成し、ミスの削減や工期の短縮に活用しています。その一例として、西村氏は次のような事例を紹介します。

画像①:MR技術を活用し、三次元データを遠隔共有できる小柳建設のツール「Holostruction」
西村氏:新潟県の小柳建設では、MRを活用し、建設生産プロセスの全データを三次元データで可視化し遠隔共有する技術を実用化しています。これは単にMRゴーグルなどで図面を現実世界に投影するだけでなく、投影した仮想的な物体を用いて、他者(遠隔も含む)とコミュニケーションや議論などを行えるツールです(画像①参照)。これにより、より現実に近い形で議論ができるだけでなく、ウェブ会議などの二次元では気づきにくいレビューなども、合わせて行えるようになっています。
さらに最近、空間コンピューティングは目覚ましく進化しており、より魅力的な存在へと成長していると西村氏は語ります。
西村氏:例えば、利用者に振動や圧力を与え、まるで現実にある物体に触れているかのような感覚を再現する技術により、利用者の没入感が飛躍的に高まっています。また、コントローラーやマウスなどを使わずに、瞳孔や手の動き、音声などを検知して連動した操作が可能なツールも登場しています。これらの技術は、現実と仮想世界や複合現実の一体感をより高めますので、さらにさまざまな用途での活用が期待されています。
このように、多くの可能性を感じさせる空間コンピューティングですが、本格的な普及には少し時間がかかりそうだと西村氏は予測しています。
西村氏:産業用途での普及は順調に進むと思われますが、一般ユーザーが常用するには、やはりゴーグルの大きさがネックになりそうです。長時間使用するには向かない重量ですし、VR酔いや眼精疲労など、身体的な不安も指摘されています。また、屋外でゴーグルを着用してひとり別の世界に没入している姿は、まだまだ目立ってしまうと思われます。日常生活に溶けこめるデザインで、かつ高性能のデバイスの登場が待たれるところです。
キーワード②:スマートロボット
自分で判断して行動できるスマートロボットの時代へ

デジタルコンサルティング部
政策・技術戦略チーム
シニアコンサルタント
木村 俊介氏
ロボットの進化も近年は目覚ましく、飲食店の配膳ロボットや接客ロボットなど、すっかり日常生活に身近な存在になりました。製造現場でも人と並んで生産ラインに立つ姿が、当たり前の光景になりつつあります。人手不足などの解決手段として存在感が高まっていますが、今後はより高性能なスマートロボットの普及が進むと予測されています。
木村氏:スマートロボットとは、AIやセンサー、通信技術などを活用することで、高度な判断力や行動力を実現した自律型ロボットを意味し、少量多品種を製造する現場では特に有効です。これまで、作業内容が刻々と変わる現場では、その度にプログラミングをやり直す必要がありました。しかし、スマートロボットはAIによって、その場の状況や指示内容を柔軟に把握し、適応することで、状況に応じた判断や行動が可能になります。
このような特性を活かして、例えば食品分野では惣菜の盛りつけなどを行うロボットの開発が進んでいます。

画像②:人型協働ロボットFoodlyは、ばら積みされた食材を一つひとつ認識してピッキングし、弁当箱・トレイへ盛りつけするまでの作業を1台で完結させる
木村氏:弁当の盛りつけは、少量多品種作業の典型です。惣菜の種類によって作業に加減が必要で、ハンバーグときんぴらごぼうでは、つかみ方や力の入れ具合などがまったく異なります。メニューも毎日変わるため、従来のロボットでは対応が困難な分野でした。しかし、スマートロボットならセンサーが食材を認識して、例えば『鶏のから揚げはこのくらいの強さでつかめば上手に盛りつけられる』と、人間が直感的に判断して行っている作業が可能になります(画像②参照)。
また物流分野の「AMR(自律走行型搬送ロボット)、介護分野の「移乗支援型ロボット」など、スマートロボットの社会実装は進んでいます。とはいえ、本格的な普及にはもう少し時間が必要だと木村氏は指摘します。
木村氏:やはりコスト面が普及のカギを握っています。高度なAIやセンサーを搭載したスマートロボット自体がまだまだ高額ですし、維持管理にかかるコストも無視できません。また導入に際しては、現場の動線や広さなどがロボットの行動に適した環境にあるか、通信インフラが整備されているかなどの検討も必要です。
キーワード③:AIの可能性
生成AIの進化形「AIエージェント」
2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれましたが、2026年はAIエージェントの普及が本格化していくと思われます。AIエージェントとは、人間のように物事を判断し、目的達成のために計画を立て、自律的に行動できるAIシステムです。従来の生成AIが、人間の入力に応じた回答を生成する存在だったのに対して、AIエージェントは単なる情報の生成にとどまらず、人間に代わってタスク(具体的な作業)を実行してくれる、まさに生成AIの進化系だと言えるでしょう。
木村氏:これまでのAIは、ユーザーの指示や質問に対する回答の生成が主な仕事でした。人間は、その回答を基に新しい設問をAIに投げかけ、会話を交わすようにステップを踏みながら、課題の解決に進みました。しかしAIエージェントは、その課題を達成するための一連のステップを自分自身で考え、データベースの操作やウェブ検索で得られたデータを分析・判断し、人間のレビューを受けながら、業務を自律的に前へ進める能力を持ちます。つまり、AIエージェントは予め設定された範囲内で、ユーザーの判断や行動まで一部代行する、文字通り頼りになる代理人だと言えるでしょう(図1参照)。

図1:AIエージェントと生成AIの特性比較
現在、AIエージェント的な機能を備えた製品として、OpenAI社が2025年にChatGPT向けに導入した「ディープリサーチ(Deep Research)」や、Microsoft社の「コパイロット(Copilot)」などがありますが、特に三つの分野で有能だと木村氏は解説します。
木村氏:AIエージェントの得意分野として、まず『調査業務』が挙げられます。例えばディープリサーチは、検索で得た情報を一回整理して、さらに検索にかけて情報をブラッシュアップしていく調査プロセスを自律的に構築する機能が特徴で、人間が数十時間かけて行う調査を数十分で完了できます。また『IT開発業務』では、アプリなどのコーディング作業※1、テスト、修正から動作確認までの一連の流れを、人間に代わって任せられると期待されています。このほか請求書や領収書の書類処理など、流れが定型化している『バックオフィス業務』の代替にも、AIエージェントは適していると言えるでしょう。
AIの進化を揺るがす「2026年問題」
2026年問題」とは、LLM(大規模言語モデル)などのAIが学習に使う高品質なデータが、数年内に底をつくかもしれないという深刻な事態を意味します。米国の研究グループ「Epoch AI」が2022年に提唱し、2023年カリフォルニア大学バークレー校のスチュアート・ラッセル教授が国連のAIサミットで警鐘を鳴らしたことで、一気に注目されました。
木村氏:AIの進化には学習データが欠かせませんが、高品質なデータが将来的に枯渇してしまう可能性があります。高品質なデータとは、学術論文、書籍や新聞の記事など、一般的に内容の信頼性が高いと言われているものです。一方で、SNSなどで誰でも投稿が可能な文章などは信憑性に乏しく、文章の質も保証されないため、これまでAIの学習には使用されませんでした。しかし、良質なデータを食べつくしたAIは、低品質なデータも学習に使用するようになり、結果として質の低い文章の特徴を再現してしまい、信頼性を損なう危険性があると懸念されているのです。
現在「2026年問題」の回避に有効な技術として、「合成データ」「フィルタリング」などの研究が進んでいます。
木村氏:『合成データ』とは、実在する良質なデータと似た傾向を持つデータをAIで人工的に生成したデータです。合成データは良質なデータを基に生成されますので、信頼性が高く情報流出のリスクの軽減にも有効と期待される技術であるため、AIの学習に適していると考えられています。また『フィルタリング』は、玉石混交なデータの中から高品質なものを選別する技術です。表現内容や法的に問題のある有害コンテンツを制限し、AIの学習に適したデータを抽出します。また文法的な不自然さや誤記を修正する能力にも長けているため、データ品質の確保に有効な技術です。
AIと社会が共存するために必須の「AIガバナンス」
そして2026年は、AIを運用・開発、利用する者に関するガバナンスのあり方が、積極的に議論される年になりそうです。特に留意すべき点について、木村氏は次のように指摘します。
木村氏:まず、生成AIが事実と異なることをあたかも事実であるかのように答える『ハルシネーション』現象が挙げられます。海外では、弁護士が法廷でAIが作成した架空の裁判例を引用してしまった事案が、複数発生しています。国内でも、自治体が試験的に生成AIで作った観光PRのページで、存在しない観光地が紹介されてしまうという事態が発生しました。
ハルシネーションの実害は、人間がAIの出力をきちんと確認することで最小限に抑えることは可能です。しかしAIの性能があまりに高すぎるため、「間違っているわけがない」と頭から信じ込んでしまい、つい検証を怠ってしまうのも人情です。こうしたリスクに対しては、AIが参考資料を検索して根拠に基づいて出力を行うような仕組み(RAG/ラグ)の導入等の技術的な対策や、万一ハルシネーションを見逃したときに発生するリスクを事前に評価する体制の構築等、多層的な取組が重要になります。
このほか、会社の業務での利用 を 認 められて い な い 生成AI(シャドーAI)に起因する、情報流出のリスクも見逃せません。
木村氏:特に無料のAIツールでは、入力した情報は今後のAIの学習データとして使ってもよいという設定になっている場合もあるため、最悪の場合、無警戒に入力してしまった会社の機密情報が他人の出力データに反映されてしまうといった危険性があります。
また、生成AIの出力を使用する際、意図せず著作権や肖像権を侵害したり、フリーソフトウェアのライセンス違反を犯してしまう「法務面」のリスクも見逃せません。このほか、過度に外部のAIモデルやサービスに事業を依存している場合は、サービスの停止や価格、使用条件の変更などで「事業継続」にダメージを受けるリスクも想定しておく必要があるでしょう。
小規模だが軽量な「SLM」の可能性
AIのビジネス活用が広まる中、これまでは主にChatGPTなどに代表されるLLM(大規模言語モデル)が基盤技術として活用されてきました。しかし、近年はLLMの中でも比較的小規模であるSLM(小規模言語モデル)に注目が集まっており、2026年はSLMの使用シーンが増えていくと考えられます。その理由について、木村氏は次のように解説します。
木村氏:LLMは大量のテキストデータから学習しているため、パラメータ数(AIの能力を示す単位)が多く、それだけ広汎な用途で活用でき、高い推論性能が期待できます。しかし、パラメータ数が大きいAIは推論に時間がかかりますし、稼働には高価な演算装置やサーバーが必要となります。また最近は、電力消費量やCO₂排出量の増加が、社会的にも問題視されています。そこで、新たな選択肢としてSLMが台頭してきています。

【図2:巨大LLMとSLMの特性比較】
SLMはLLMとしては規模が小さいものの、プロンプト※2を入力して文字が出力される機能は同じです。そして、SLMは規模が小さいためにデータ容量も軽いという特徴があり、一般的なLLMに比べてさまざまなメリットがある(図2参照)と、木村氏は語ります。
木村氏:身軽なSLMの最大の武器はスピードです。そのため、顧客サポートなどのレスポンスが重視される分野では、巨大なLLMよりSLMの方が有利だと言えるでしょう。また、特定の分野を深く学び、その分野における利用に特化すれば、巨大LLMに迫るパフォーマンスを発揮することも可能です。
また、AIガバナンスの話題でも触れましたが、AI利用には情報流出の危険性が伴います。そのリスクを考慮するとLLMをオンプレミス※3環境で稼働させる「ローカルLLM」には大きなメリットがあるのですが、巨大なLLMを運用するには高性能なサーバーが不可欠なため、企業の利用の多くはクラウド経由に限られていました。このような場面においても、SLMの可能性は広がると考えられます。
木村氏:ローカルLLMの最大のメリットは、セキュリティの高さです。データが外部に送信されないため、機密情報漏洩のリスクが少なく安全なAI活用が実現します。通信による遅延が発生しないことも利点のひとつです。そのため、医療業務やロボット操作など、リアルタイム性が求められる業務の需要が高いと想定されています。
より安全でより高性能な「国産AI」の登場に期待
AIの開発はアメリカと中国が先行しているため、これまでは海外製のシステムに頼るのが一般的でした。しかし、これには大きなリスクがあり、私たちは常に海外へのデータ漏洩や日本に関する誤情報が拡散されるといった不安にさらされています。そこで近年は、政府が学習データなどの開発資源を日本企業に提供して、国産AIの開発を支援する動きが活発になってきました。現在、ゼロから国内で開発されたAIが、NTT(tsuzumi)、日本電気(cotomi)、Preferred Networks(PLaMo)、SB Intuitions(Sarashina)などからリリースされています。さらにNTTからは「tsuzumi」の次世代型として、小型ながらも日本語性能では巨大モデルに匹敵する純国産LLM「tsuzumi 2」が昨年10月に提供開始されたことも記憶に新しいところです。
木村氏:生成AIは、企業や官公庁の日常業務に浸透しつつあり、今後、生成AIがなければ社会がうまく回らなくなる、一種の『インフラ』に近いものになると思われます。その技術が海外の企業に掌握されてしまうと、地政学的な関係で突然提供が受けられなくなるなどのリスクがあります。また、重要インフラや防衛に関わる極めて機微な情報を扱うケースでは、海外企業が管理するツールの使用が許容できない場合もあります。そのため、性能が高い生成AIを国内で供給できるようにすることは、非常に重要な意義があります。
しかし、自由経済の中でビジネス活動を行い、生き残っていくためには、機密情報を扱う場合を除き、海外産か国産かを問わず性能やコストパフォーマンスの高さが選択肢の主要因になると思われます。2026年は、その厳しい競争の中で国産AIが勝ち抜いていく姿に期待したいものです。
- ※1 コーディング作業
- プログラム言語を使用し、コードを記述していく作業のこと。
- ※2 プロンプト
- AIに指示や質問を与えるためのテキスト。利用者がAIに何を求めているかを具体的に伝える役割を有し、プロンプトの質や明確さがAIからの出力の精度を左右する。
- ※3 オンプレミス
- サーバーやネットワーク機器、ソフトウェアなどを自社で保有し運用すること。

| 会社名 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2004年(平成16年)10月1日 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-3 |
| 取締役社長 | 吉原 昌利 |
| 事業内容 | リサーチ、コンサルティング、ITコンサルティング、ITソリューションなど |
| URL | https://www.mizuho-rt.co.jp/ |
関連記事
-
![-株式会社NTTコノキュー-<br>企業の課題解決の切り札として期待されるXRの可能性とは]()
-
![-株式会社NTTPCコミュニケーションズ-<br>真夏の猛暑から従業員を守るICTを活用した熱中症対策]()
2024.07.25 公開
-株式会社NTTPCコミュニケーションズ-
真夏の猛暑から従業員を守るICTを活用した熱中症対策熱中症への対策が、企業にとって喫緊の課題となっています。特に建設業や製造業など、...
-
![-西日本電信電話株式会社(NTT西日本)-<br>大容量で低遅延、消費電力も大幅カット 次世代へ向けた「IOWN構想」で叶える未来]()
2024.04.25 公開
-西日本電信電話株式会社(NTT西日本)-
大容量で低遅延、消費電力も大幅カット 次世代へ向けた「IOWN構想」で叶える未来通信業界では今後、高度な情報処理によるデータ通信量の増加に伴い、増え続ける消費電...
-
![-内閣府 宇宙開発戦略推進事務局-<br>日本版GPS「みちびき」から広がる新しいビジネスの可能性]()
2024.03.26 公開
-内閣府 宇宙開発戦略推進事務局-
日本版GPS「みちびき」から広がる新しいビジネスの可能性スマホの地図アプリや車のカーナビは、測位衛星と言われる人工衛星が発信する電波を受...
-
![-株式会社ストロボ-<br>自動運転の「レベル4」解禁によるクルマ社会の新たなビジネスの可能性を探る]()
2023.06.26 公開
-株式会社ストロボ-
自動運転の「レベル4」解禁によるクルマ社会の新たなビジネスの可能性を探る2023年4月1日より改正道路交通法が施行され、自動運転「レベル4」の公道走行が...