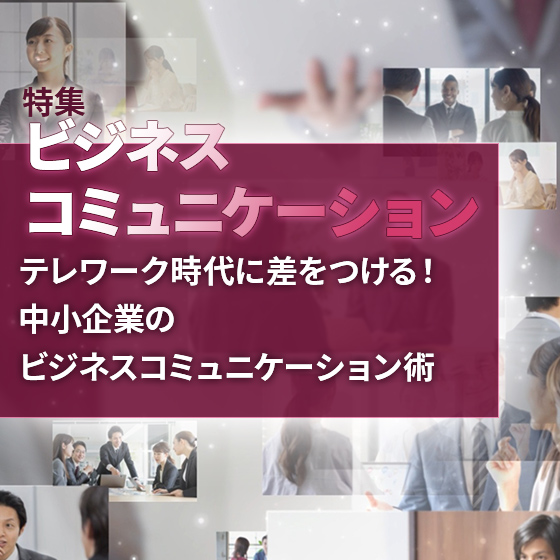ICTソリューション紹介
-株式会社Medi Face-Z世代の休職・離職が増加する中必要性が高まるメンタルヘルスケア対策
記事ID:D10052

近年、Z世代※1と呼ばれる20代~30代の若者が、「メンタル面の不調」を理由に入社後間もなく休職・離職する事例が増加しています。また世代を問わず、職場でストレスを感じている従業員の数は増加する一方です。このような状況を打開するために、ICTやAIサービスを導入して従業員の心の健康維持を図る企業が増えています。AIによるメンタルヘルスケアに取り組む、株式会社Medi Faceの代表取締役で精神科医でもある近澤 徹氏に、現況をうかがいました。
メンタル面に不調を抱えるビジネスパーソンが増加中

代表取締役 近澤 徹氏
企業が従業員の心の健康をサポートする、メンタルヘルスケアの重要度が増しています。厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、職場生活で強い不安や悩み、ストレスを感じている従業員の割合は、82.7%となっています。メンタルヘルスの不調で連続1ヵ月以上の休職または退職した労働者がいた事業所は、13.5%を記録しました。また、同省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」によると、仕事によってうつ病などの精神障害を発症し、労災認定を受けた件数は8 8 3件に達し、5年連続で過去最多を更新しています。
このような動向はここ2、3年でより加速傾向にあり、精神的に疲れている従業員の心を守り、休職や離職に至らせないためにも、企業は早急に効果的なメンタルヘルスケアを実施する必要があると近澤氏は語ります。
「2 0 2 0年のコロナ禍をきっかけに、メンタル面に不調を抱える人の数が世界的に増えており、日本でも約2倍に増加しています。リモートワークが当たり前の勤務スタイルになり、対面での会話や飲み会などのリアルな交流機会が減ったことで孤立感が醸成され、メンタル面に悪影響を与えたと考えられます。この傾向はZ世代により顕著で、就職して3年以内に3人に1人が離職し、その約75%が、『メンタル面の不調』を理由に挙げています。企業の生産性を確保するためにも、従業員に向けた新しいメンタルヘルスケアの実施が喫緊の課題になったと言えるでしょう」(近澤氏)
現在、従業員数が5 0名を超える企業には、1年に1回のストレスチェックが義務づけられ、メンタルヘルスケアが行われています。高ストレス者と判断された従業員から申し出があった場合には、産業医による面談も求められています。従業員のメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合も6 3 . 8%(「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」)と、企業の対策も進んでいます。しかし、今でもメンタルヘルスケアの世界には旧態依然とした先入観が残っており、従来のケアだけで従業員のストレスを軽減させるのは難しい、と近澤氏は指摘します。
「メンタルクリニックを受診していることを他人に知られたくない、という『心理的なハードル』は、今でも職場に存在しています。ストレスチェックで産業医との面談が必要と診断されたにもかかわらず、実際に受診する人は全体の約5%に過ぎません。また受診した人でも、症状に気づいてから治療を始めるまでに平均で13~17ヶ月の未治療期間があります。日本のうつ病患者数は約600万人と推定されていますが、実際に精神科を受診した人数は1 0 0万人なのです。多くの従業員が相談もできず、進行するメンタルの不調に悩みながら、働いているのが現状です。そのため、受診した時には重症化がかなり進んでいる場合が多く見られます。最悪のケースでは、いつかストレスが個人の許容量を超え、コップから水があふれるようにさまざまな症状が表れてしまいます。そして休職・離職へと向かってしまうのです」(近澤氏)
ICTやAIを活用して心理的な抵抗感を軽減
「心理的なハードル」を乗り越えるサービスとして近年は、I C Tを活用したメンタルヘルスケアが注目されています。アプリを利用してストレスチェックやメンタルヘルス診断を行うもの、オンラインで専属カウンセラーに相談できるものなどがあり、より気軽に心の健康に向き合えるサービスとして、利用者が増えています。
また、AIを導入する動きも活発です。動画を解析して従業員の心の不調を検知するサービスや、入力した日記をAI が解析し感情を可視化、心の整理やメンタルヘルスに好影響を与えるものなど、数も増えてきています。近澤氏はこれらのサービスを企業が有効に活用することで、従業員がより積極的にメンタルヘルスケアに向き合えるようになると語ります。
「I C TやA Iを活用したサービスは、ケアに必要な時間や場所の制約が緩和され、気軽さが向上しています。自分に都合の良い時間でのケアやチェックが可能になり、産業医との面談も自宅で行えるなど、従業員のメンタルヘルスに対する『心理的なハードル』は、確実に下がりました。I C TやA Iの活用でより正確なメンタル状況が把握できれば、これまでは見逃されていた軽度のうつ病患者を発見し、うつ病予備軍を事前に救えるようになると期待しています」(近澤氏)
近澤氏が代表取締役を務めるMedi Face社が提供するサービスも、A Iを活用した事例の一つです。

【図:AIドクターによるメンタルチェックの流れ】
「当社のサービス『Mente forB i z』は、2 4時間3 6 5日利用可能なA Iメンタルチェックと、健康管理のプロが対応する相談窓口の2段構えで、従業員のメンタルをサポートするものです。具体的には、長くても5分程度の簡単な問診や設問を行ない、『A Iドクター』が表情や声の調子、会話の内容から、ストレスチェックでは見えない細かな心の動きをチェックし、メンタルパワーが低い場合には産業医とのリモート面談に誘導します(図参照)。これは自分のスマホなどを使用して自宅で利用できるので、会社の上長や同僚に行動を知られる心配はありませんし、個人情報は完全に秘匿されています。サービスを導入された企業の中には、これまで産業医への相談がほぼ0%だったのが、約2 0~3 0%まで上昇したという企業もあります」(近澤氏)
メンタルヘルス対策はすべての企業で必須の時代に
昨年10月、厚生労働省はストレスチェック制度の義務化対象を、従業員50名未満の全事業所にも拡大する方針を発表しました(導入時期は未定)。一方で、50人未満の事業所でストレスチェックを実施したのは58.1%(「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」)に留まっています。
「ICTやAIサービスの導入は、経営層と現場の距離が近い中小企業こそ、より効果的な結果が期待できると感じています。中小企業の中には、なかなか健康経営※2まで気が回らない会社もあると思います。しかし弊社の調べでは、35.8%の若手従業員が、会社を評価するポイントとして『メンタルヘルスケアが行われること』、37.6%が『心理的な安全性が確保されていること』と回答しています。現代は、メンタルヘルスケアへの取り組み方が、企業イメージや就職希望者の応募状況を左右する時代なだけに、積極的な対応の必要性を感じます」(近澤氏)
まもなく、従業員のメンタルヘルスケアがすべての企業において義務となる時代がやってくる予定です。まずは休みや遅刻が増えている若手従業員や、仕事に追われる中間管理職など、ストレスを抱えているように見える従業員の相談に乗るところから、メンタルヘルスケアの実践に取り組み、ICTやAIサービスの導入を検討してはいかがでしょうか。
- ※1 Z世代
- 1990年代半ば~2010年代序盤生まれの世代。生まれた時点でインターネットが普及していてデジタルネイティブ、S N Sネイティブとも呼ばれ、効率主義などの特徴的な価値観を持っている。
- ※2 健康経営
- 従業員の健康維持や増進が、企業の収益性や価値の向上につながるとの考えから、健康管理を経営的視点で実践するもの。

| 会社名 | 株式会社Medi Face |
|---|---|
| 設立 | 2020年(令和2年)5月18日 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7階 |
| 代表取締役 | 近澤 徹 |
| 事業内容 | 人工知能の活用による医療及びヘルスケア関連ソフトウェア、各種システムの企画及び研究、開発、制作、配信、保守、管理、運営、販売、導入支援及びそれらの受託など |
| URL | https://medi-face.co.jp/ |
関連記事
-
![-一般社団法人スマートフードチェーン推進機構-<br>データ連携がもたらす効率化と付加価値を生むスマートフードチェーンの現在と展望]()
2025.10.27 公開
-一般社団法人スマートフードチェーン推進機構-
データ連携がもたらす効率化と付加価値を生むスマートフードチェーンの現在と展望近年、食品業界では食の安全性に対するニーズへの対応や、減少する労働力を補うために...
-
![-防災DX官民共創協議会-<br>官民が連携した防災DXに期待される新しい防災スタイルとビジネスモデル]()
2025.07.25 公開
-防災DX官民共創協議会-
官民が連携した防災DXに期待される新しい防災スタイルとビジネスモデル近年、大地震や集中豪雨などの自然災害が、多くの被害を全国各地にもたらしています。...
-
![-株式会社コークッキング-<br>ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目]()
2025.05.26 公開
-株式会社コークッキング-
ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目食品の売れ残りの処理が環境に悪影響を及ぼし、経済損失を生む「食品ロス」の問題が深...
-
![-株式会社船井総合研究所-<br>2025年、クラウド活用の新潮流]()
-
![-福井県観光DXコンソーシアム-<br>宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」]()
2024.08.26 公開
-福井県観光DXコンソーシアム-
宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」観光地では昨今、観光で地域全体の稼ぐ力を高めるため、デジタル技術を駆使しながら自...