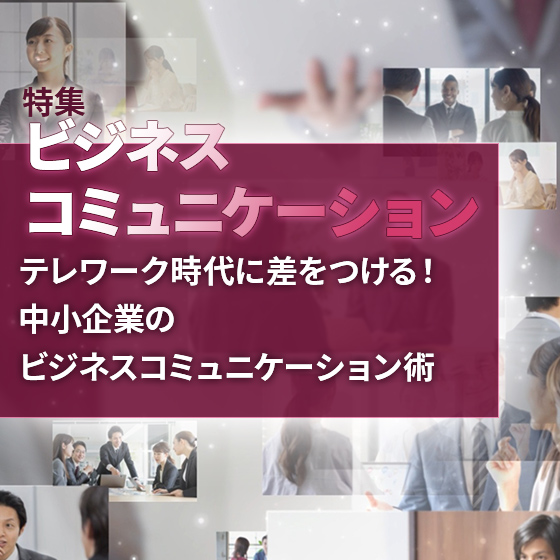ICTソリューション紹介
-防災DX官民共創協議会-官民が連携した防災DXに期待される新しい防災スタイルとビジネスモデル
記事ID:D10055

近年、大地震や集中豪雨などの自然災害が、多くの被害を全国各地にもたらしています。こうした災害の被害を軽微にとどめ、速やかに復旧させていくためにDXを取り入れ、より効率的な防災を実現する取り組みが注目されています。今回は、デジタル庁の声がけにより民間事業者・自治体などで発足した「防災DX官民共創協議会」で、理事長を務める臼田 裕一郎氏に、防災DXの重要性や産業化の可能性などについてうかがいました。
公助に頼り過ぎない防災システムが必要

理事長 臼田 裕一郎氏
近年の自然災害はますます巨大化、頻発化、複雑化しており、現在でも多くの被災地で、被害への対応や復旧が進められています。また、30年以内に80%程度の確率で発生すると想定される「南海トラフ巨大地震」など、今後起こりうる自然災害への対策も急務です。内閣府の中央防災会議は今年3月、南海トラフ巨大地震の被害想定を、最悪のケースで約30万人が死亡、経済的な被害額は約300兆円弱に上ると公表しました。このような危機を前にして、「防災DX官民共創協議会」(以下BDX)の臼田氏は、これまでの防災システムだけで激甚化する自然災害に対応するのは限界があると語ります。
「これまで日本の防災は、自治体の避難所や消防、警察、自衛隊の支援といった、公的機関の『公助』と呼ばれる救援システムを基盤に成り立っていました。しかし現在、地域の防災を担う自治体の人手不足や資金不足は深刻で、その防災能力は脆弱化傾向にあり、対応が難しくなりつつあります。実際に、2018年に発生した『西日本豪雨』を受け、中央防災会議がまとめた『平成30年7月豪雨を踏まえた 水害・土砂災害からの避難のあり方について (報告)』には、公助の限界が明記されました」(臼田氏)
こうした現況を背景に、従来は人海戦術や人の手で行ってきた作業などをデジタル化する防災DXのニーズは高まっています。そして、この防災DXをより効果的に行うため、BDXは国や自治体、企業などの枠を超えた新しい防災DXの姿を目指していて、会員数は現在地方公共団体と、民間事業者など530者を超えています。
「公助に頼った防災の限界が示された今、防災は社会全体で取り組むテーマになりました。そのためには官民との協働が欠かせません。特に民間は高度なデジタル技術を保有しています。例えば官が提供するデータと民間のデジタル技術が連携すれば、より強力な防災DXが実現します」(臼田氏)
地震のたびに課題になる情報共有のための標準化

画像①/能登半島地震時のBDX拠点(石川県庁5階)の様子
2024年能登半島地震の時も、BDXは直ちに災害派遣チームを編成し、石川県庁内に拠点を構えて災害支援活動を開始しました(画像①参照)。BDXがまず取り組んだのは「避難所情報の把握」です。能登半島地震では道路網が大きな被害を受けて移動が困難になる中、元日で多くの帰省者がいたため、自治体が用意した指定避難所以外にも多くの自主避難所が開設されていました。しかし、その情報が共有されていなかったため、どこに避難所が存在しているかがわからず、救護活動のロスが生じていたのです。
「能登では自治体、DMAT(災害派遣医療チーム)、自衛隊がそれぞれで避難所一覧を作成し、活動を展開していました。災害時には地方自治体や各公的機関などの組織が同時並行で活動することが多いため、各機関間での情報や状況認識の共有が進まないと、作業が非効率になるという課題があります」(臼田氏)
さっそく、BDXはすべての情報を網羅した避難所マップの作成に取りかかりましたが、作業は困難を極めました。
「三者の情報を単純に統合すれば、全体の避難所マップが完成するというものではありません。情報が重複していたり、場所が同じでも名前や数字が違っていたり、把握した時刻も違うなどの問題があり、全体の把握にとても苦労しました。実は2016年の熊本地震の際にも同じような状況があったのですが、8年もの間、問題が解決されなかった事実に愕然としました。改めて組織を横断した基盤的データの必要性が浮き彫りになったのです」(臼田氏)
そこでBDXは、三者で管理され重複などで把握できていなかった避難所情報を集約・可視化するアプリを、民間業者の協力を得て3日で開発しました。アプリによって、住所や位置などの情報でマッチングして、同一のものと推定される避難所情報を明確にし、それらを精査することで1,598ヵ所とされていた避難所の数を917ヵ所に確定することができました。この情報は石川県総合防災情報システムに掲載され、広く活用されています。
「公的機関と民間の技術力の協業が新しい防災DXの誕生につながっています。この点は熊本地震の頃より大きく進歩したところだと考えています」(臼田氏)
災害現場で重宝された民間のデジタル技術

画像②/被災地に提供された「スターリンク」の台数は、最終的には350台にもなった。一部は臼田氏自身も設置した
避難所情報の把握と並行して避難者情報の把握も行われました。すでに帰宅した人、他の地域に移動した人など、二次避難が始まった被災地では、避難者の居場所が広域化し、正確な動向が把握しづらくなっていたのです。そうなると支援物資の的確な配布など、効率的な運営に支障をきたす恐れがあります。
そこで活用されたのが、JR東日本の交通系ICカード「Suica」でした。一次避難所の利用者にSuicaを配布して氏名や住所などの情報を登録し、避難所や食堂、入浴施設などを利用する際にカードリーダーにタッチすることで、誰がどこでどのような支援を受けたかが分かり、最新の避難状況をオンタイムで把握することが可能になりました。
また今回、被災地を悩ませたのが、通信回線の分断でした。能登では通信基地局の停電や損傷により、多くの拠点で通信途絶が発生しました。そこでBDXは衛星インターネット回線「スターリンク」の受信機器を設置し、現場の通信環境を構築しました。
「衛星インターネット回線は、今回の災害対応でかなり重宝しました。人工衛星を通した通信なので、地震の影響を受けず被災地でも分断の心配がありません。また、従来の災害時用の通信には特殊な装置が必要で、限られた人間でしか扱えませんでしたが、衛星インターネット回線なら普段使用している自分のパソコンやスマホが問題なく使えるため、快適な通信環境を確保できました(画像②参照)」(臼田氏)
災害時をも想定した商品開発に期待したい
BDXの防災DX活動には、多くの民間企業が参加しています。活動は長期にわたるものも多く、民間企業にかかる経済的な負担は無視できません。それだけに防災DXからビジネスを生み出し、民間企業の持続的な活動を支える必要があります。しかし臼田氏は、防災の当事者である市町村などの自治体に防災関係の商品を売り込むといった、従来型のビジネスモデルは難しいと指摘します。
「どの市町村も財政的に苦しい状況にある上、発生するかしないか分からない災害を念頭においた商品やサービスには消極的です。一方、『この商品は平時の使用を想定していますが、実は災害時にも使用可能な性能や耐久性を有しています』といったフェーズフリー、すなわち平時と災害時の垣根を取り払った発想による商品開発にビジネスチャンスがあるかもしれません。例えばキャンプ用品や生活用品の中には、『災害時にも使えます』をうたい文句にした商品がすでに登場しています」(臼田氏)
例えば災害時の救援活動を想定したロボットが、平時には介護ロボットとして福祉施設で活躍するビジネスモデルなど、さまざまな商品開発に期待がかけられています。このように災害が多い日本ならではのビジネスモデルを考えていくことが、より効果的な防災DXを構築する上でのカギになりそうです。
| 組織名 | 防災DX官民共創協議会 |
|---|---|
| 設立 | 2022年(令和4年)12月 |
| 事務局 | 東京都千代田区永田町2-10-3(株式会社三菱総合研究所内) |
| 理事長 | 臼田 裕一郎 |
| 事業内容 | 防災におけるデータ連携などの推進を通じた住民の利便性の向上を目指し、防災のデータアーキテクチャの設計やデータ連携基盤の構築などの検討を行う協議会 |
| URL | https://ppp-bosai-dx.jp/ |
関連記事
-
![-一般社団法人スマートフードチェーン推進機構-<br>データ連携がもたらす効率化と付加価値を生むスマートフードチェーンの現在と展望]()
2025.10.27 公開
-一般社団法人スマートフードチェーン推進機構-
データ連携がもたらす効率化と付加価値を生むスマートフードチェーンの現在と展望近年、食品業界では食の安全性に対するニーズへの対応や、減少する労働力を補うために...
-
![-株式会社コークッキング-<br>ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目]()
2025.05.26 公開
-株式会社コークッキング-
ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目食品の売れ残りの処理が環境に悪影響を及ぼし、経済損失を生む「食品ロス」の問題が深...
-
![-株式会社Medi Face-<br>Z世代の休職・離職が増加する中必要性が高まるメンタルヘルスケア対策]()
2025.04.25 公開
-株式会社Medi Face-
Z世代の休職・離職が増加する中必要性が高まるメンタルヘルスケア対策近年、Z世代※1と呼ばれる20代~30代の若者が、「メンタル面の不調」を理由に...
-
![-株式会社船井総合研究所-<br>2025年、クラウド活用の新潮流]()
-
![-福井県観光DXコンソーシアム-<br>宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」]()
2024.08.26 公開
-福井県観光DXコンソーシアム-
宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」観光地では昨今、観光で地域全体の稼ぐ力を高めるため、デジタル技術を駆使しながら自...